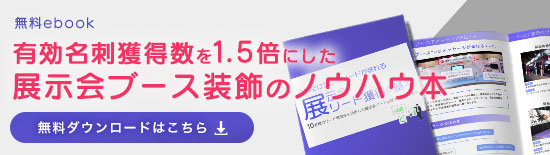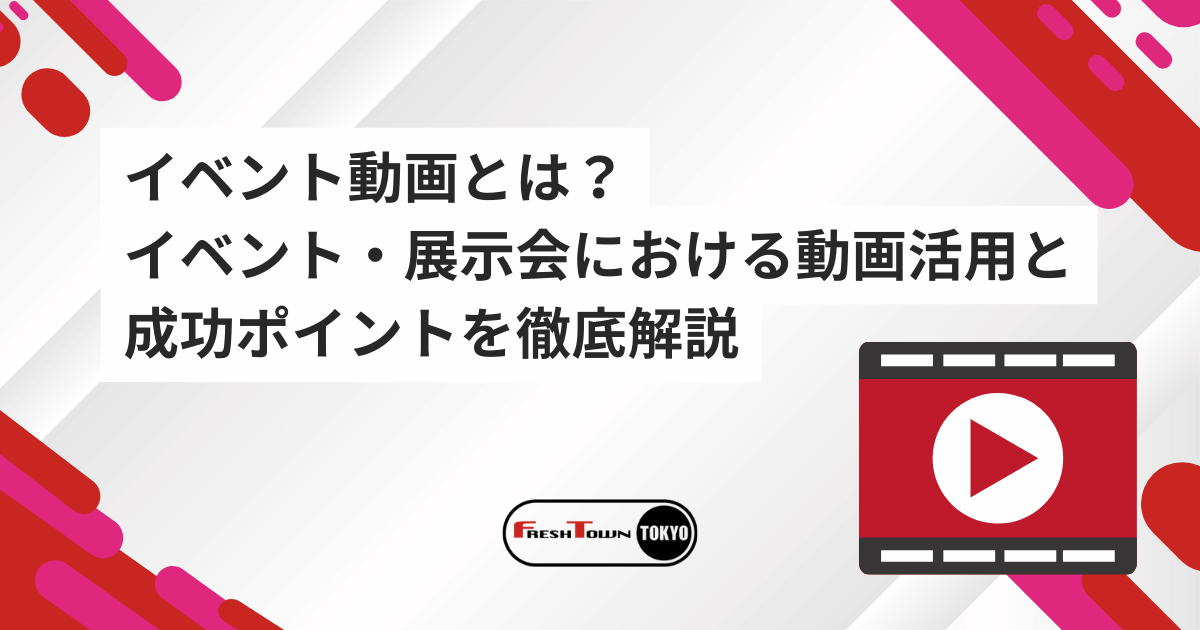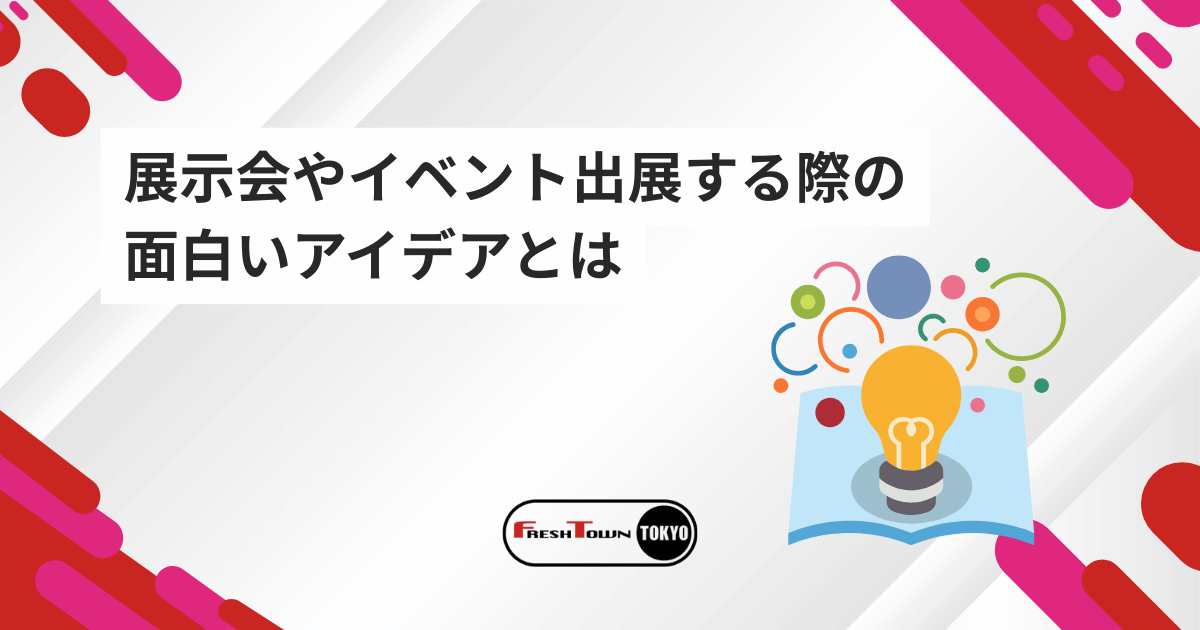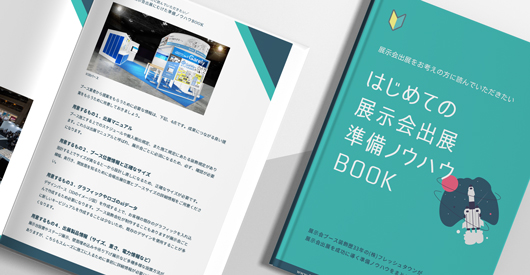展示会の効果的な活用方法を徹底解説!
INDEX

展示会は、企業が新たな顧客や見込み案件を獲得し、製品やサービスを直接来場者にアピールできる貴重なビジネスチャンスです。特にBtoB業界においては、展示の場を活用することで、商談の機会を創出し、関係者との接点を増やすことができます。
本記事では、展示会をマーケティング施策として戦略的に活用し、確かな成果を上げるための具体的な方法を解説します。出展の目的や準備の段階から、当日の対応、終了後のフォローアップまで、各ステップで押さえるべきポイントや工夫を紹介します。
また、SNSや動画といったデジタルツールとの連携による効果的な施策や、失敗を防ぐための注意点にも触れながら、展示会を成功へと導くためのアイデアもあわせてご紹介します。
展示会の目的と目標を明確にする
展示会に参加するうえで最初に取り組むべきは、出展の目的と目標を明確に設定することです。目的が不明確なままでは、準備の段階から軸がぶれてしまい、結果として成果を得られないまま終わるリスクが高まります。
主な目的には以下のようなものがあります。
・ 新規顧客の獲得
・ 既存顧客との関係強化
・ 新製品の認知度向上やテストマーケティング
・ パートナー・代理店との接点づくり
・ ブランドのアピールやポジショニングの確立
さらに、数値目標を設定することも重要です。たとえば「会期中に名刺交換を100件以上行う」「10件以上の商談を発生させる」など、定量的なKPIを定めることで、効果の分析や改善にもつながります。
また、目的に応じた告知やコンセプト設計も必要です。来場者の興味や関心を引くテーマやキャッチコピーを用意することで、集客の効率も高まります。
出展前に検討すべき種類とターゲット
出展の検討段階では、展示会の種類や、ターゲットとなる来場者層を明確にする必要があります。業界によっては技術展示会、合同展示会、展示即売会などさまざまな形態が存在します。それぞれの特徴や目的に合わせて選ぶことで、自社にとって最適なビジネス環境を整えることができます。
ターゲット設定では以下の要素を検討します。
・ どの業界に属する企業か
・ どのような課題を抱えているか
・ どの製品・サービスに関心を持つ可能性があるか
・ どのような意思決定権を持つ担当者が来場するのか
これらを整理したうえで、案内状やDMなどの事前施策を講じ、来場を促すことが重要です。競合他社との差別化も意識しておくと、会場内での存在感が高まります。
成果を最大化するための準備とブース設計
展示会で高い成果を得るためには、事前の準備が鍵を握ります。まず取り組むべきは、ブースのデザインと設計です。通路や隣接ブースとの位置関係を考慮し、来場者が立ち寄りやすいレイアウトや装飾を意識することで、印象や興味を持たせることができます。
また、ブランドのイメージを視覚的に伝えるため、パンフレットやフライヤー、ノベルティなどの制作も抜かりなく行う必要があります。とくに視覚的な要素が重要な展示会では、映像やデモンストレーションを通じて製品の価値を体験してもらう工夫が求められます。
タイムスケジュールの策定や備品の手配、設営スケジュールなども含めて、早めの計画が成功を左右します。さらに、イベント全体のコンセプトに沿った演出を行うことで、他社との差別化につながります。
事前準備とスタッフ配置のポイント
スタッフの配置と役割分担も展示会の成否を左右する重要な要素です。営業担当や技術担当など、複数の視点から来場者に説明できるようにしておくと、より幅広い関心に対応できます。
以下のような体制を整えることが理想です。
・ 受付担当:名刺交換や案内対応
・ 製品担当:デモや製品説明、質疑応答
・ 商談担当:見込み顧客との会話・アプローチ
また、対応の一貫性を保つために、事前にトークスクリプトを用意したり、ロールプレイングによる事前訓練も有効です。さらに、MAツールや管理シートを使って、名刺やアンケート情報をその場で記録・整理できる体制を整えておくと、フォローアップもスムーズになります。
集客につながる当日の対応とブース活用
展示会当日は、限られた時間内で多くの来場者と接点を持つ必要があるため、対応の質とスピードが問われます。来場者の足を止めるには、ブースの雰囲気づくりが重要です。視覚的に訴求できる装飾や、体験型のデモンストレーションを取り入れることで、より多くの人の関心を引くことができます。
また、当日はリアルタイムでSNSを活用することも効果的です。ハッシュタグを活用した発信や、ブースの様子を動画で投稿することで、会場にいないユーザーにも情報を届けられます。これにより、Webやホームページへの導線を作り、オンラインとの連動による集客力の強化が期待できます。
さらに、プロモーションとして特典やノベルティを用意しておくことで、来場の動機付けや記憶に残る印象を与えることができます。
来場者対応とSNS・動画の連動活用法
来場者対応では、担当者ごとに明確な役割を決めるとともに、一人ひとりの興味やニーズに合わせた会話を心がける必要があります。特にBtoBの場では、形式的な対応ではなく、課題を聞き出すようなコミュニケーションが信頼関係の構築につながります。
SNSやYouTubeなどのメディアで展示会の様子を紹介することで、業界関係者や競合他社も含めた広い層への認知拡大が可能です。ライブ配信やショート動画でブースの魅力や製品の特徴を訴求することで、展示の効果を最大化することができます。
また、動画の再利用も視野に入れ、展示後に案内やDMで見込み顧客へ送付するなど、継続的なアプローチにもつなげることができます。これにより、当日の対応だけでなく、その後の営業活動にも好影響をもたらします。
商談・顧客獲得につなげるフォローアップ方法
展示会は出展して終わりではなく、終了後のフォローアップこそが顧客の獲得と商談の成立に直結します。名刺交換や会話を通じて得た情報をもとに、見込みの高い相手には優先的にアプローチすることが重要です。リードのランク付けや、情報の管理にはMAツールやCRMを活用すると効率的です。
まずは、展示会終了後、できるだけ早くメールや電話でお礼を伝え、来場のお礼や当日の資料の送付を行いましょう。この時点でのレスポンスが早いほど、関係性を維持しやすくなります。加えて、案内状や次回展示会の案内など、継続的な接点づくりも効果的です。
商談に進みそうな相手には、課題に応じた提案や説明を行い、相手のニーズに寄り添ったアプローチを展開することで受注の可能性が高まります。
メールや資料を使った終了後のアプローチ
フォローアップの中心となるのがメールと資料による情報提供です。展示会では短時間の会話で終わることが多いため、後から改めて詳細な情報を提供できるよう、パンフレットや導入事例、最新の事業内容をまとめたコンテンツを送付しましょう。
以下のようなポイントを意識したメールが効果的です。
・ 個別対応を意識した宛名と内容
・ 展示会での会話内容の簡単な振り返り
・ 相手に合わせた製品情報・事例の紹介
・ 次のアクション提案(訪問・オンライン打ち合わせなど)
また、送付する資料にはデザインや構成にも配慮し、ブランドのイメージをしっかりと伝えられるようにすることが求められます。WebページへのリンクやYouTube動画と連動させるのも効果的です。これにより、見込み顧客に対して複数の情報提供チャネルを確保できます。
展示会を成功に導くためのアイデアと注意点
展示会で確かな成果を得るためには、基本的な手法に加えて、柔軟なアイデアと的確な対応が求められます。近年では、オンラインとのハイブリッド開催や、セミナー併設型のイベントも増加しており、企画の自由度も高まっています。限られた費用やリソースのなかで、いかに効果的な施策を実行できるかが成功の分かれ道になります。
たとえば、ショー的な演出を組み込んだブースや、体験型コンテンツによって、来場者の記憶に残るような工夫が効果的です。来場者とのコミュニケーションを深めるために、インタラクティブなツールを導入するのも良い方法です。
また、競合の出展状況や業界のトレンドを把握したうえで、差別化を図る視点も重要です。他社が行っていないPR戦略や、ホームページとの連動などを取り入れることで、認知の拡大とビジネスへの転換率を高めることが可能になります。
よくある失敗と効果的な改善方法
展示会でよく見られる失敗例としては、以下のようなものがあります。
・ 目的やターゲットが曖昧で、準備段階から軸が定まらない
・ ブースが目立たず、来場者が立ち寄らない
・ スタッフが対応しきれず、名刺交換や説明のチャンスを逃す
・ フォローが遅れ、見込み顧客との関係が途絶える
・ 資料が一般的で、相手のニーズに合っていない
こうした課題に対する改善方法としては、開催前のデータ分析に基づいた計画立案や、通路からの誘導を意識した配置、そして展示内容に合わせたキャッチコピーやテーマ設定が挙げられます。
また、終了後のアンケート結果を活用して、次回以降の展示会での施策をブラッシュアップしていくことも重要です。KPIの見直しや、案件管理の方法改善など、PDCAを回す仕組みを社内で整えることで、継続的な成果向上が期待できます。
まとめ:展示会で確実に成果を上げるために必要なこと
展示会は、ただ参加するだけでは成果を上げることは難しく、明確な目的設定と戦略的な準備、そして適切なフォローアップが必要です。出展前のターゲット選定やブースの設計、スタッフの配置と役割分担など、事前段階からしっかりと準備を整えることが成功の第一歩となります。
また、当日の対応では、来場者とのスムーズなコミュニケーションと、記憶に残る体験提供がポイントです。リアルタイムでのSNSや動画による情報発信も、ブランドの認知や興味喚起に効果的です。
さらに、展示会後のメールや資料を用いたフォローによって、得られたリードを商談や受注につなげることが可能です。継続的な関係構築と改善を意識することで、展示会を一過性のイベントではなく、確実にビジネスを前進させるマーケティングの柱として活用できます。
☞展示会を成功へ導く!成果を最大化するためのポイント
・ 出展目的と数値目標を明確に設定し、戦略的な準備を行う
・ 展示会の種類やターゲットに合わせて、最適な会場選びと施策設計を進める
・ 目を引くブース設計とスタッフ配置により、来場者との接点を最大化する
・ SNSや動画を活用し、リアル・オンラインの両面から集客力を強化する
・ 展示会後は迅速なフォローアップで商談化・顧客獲得を目指す
・ 成果分析とPDCAサイクルによって、次回以降の施策改善を図る
・ 「準備・実施・フォロー」の一貫した取り組みがビジネス成功への鍵となる
展示会を成功させる鍵は、「準備・実施・フォロー」の一貫した設計にあります。これらを的確に行うことで、展示会は単なる情報発信の場ではなく、ビジネスチャンスを創出する強力な手段となります。
お役立ち資料
CASE STUDY
創業以来培ったノウハウとデータをもとにまとめたハンドブックです。
「初めての展示会で何をやったら良いかわからない」「効率的に成果を出すブースづくりについて知りたい」、そんな方におすすめです。
本資料は展示会出展社さま、展示会出展をご検討されている方に向けて作成した資料です。 同業他社さまには資料ダウンロードをご遠慮いただいております。申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。