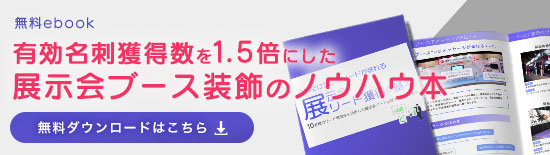展示会で映像を活用するメリットと効果とは?|映像演出が集客に好影響を与える
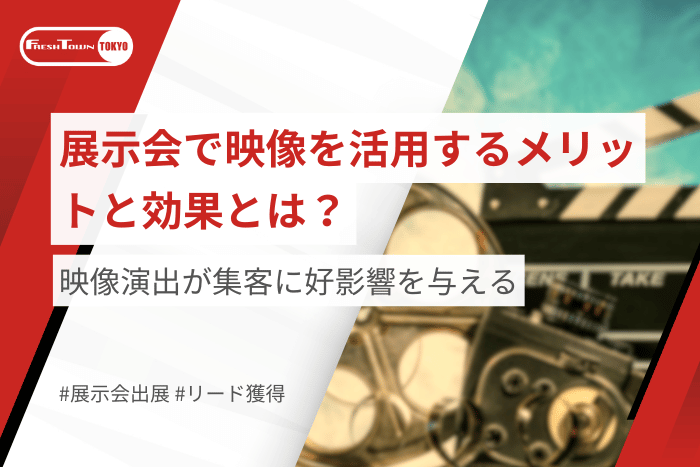
展示会やイベントは、企業が新製品やサービスを直接アピールし、来場者との接点を築く重要な機会です。その中でも、映像を活用したプロモーション手法は、視覚的なインパクトと情報量の多さから注目されており、多くの企業が積極的に取り入れています。
特に近年では、実写やアニメーション、CGなどの多彩な映像表現が可能となり、単なる「紹介」にとどまらず、ストーリー性を持った演出やブランドイメージの訴求など、多様なアプローチが実現できます。こうした映像の活用は、展示会において集客力を向上させるだけでなく、製品やサービスへの理解を深め、商談にもつながる効果が期待されます。
本記事では、展示会で映像を活用するメリットや効果的な手法、制作時のポイントや成功事例までを体系的に解説します。展示会で成果を出したいと考える担当者の方にとって、実践的なヒントとなる内容を詳しく紹介していきます。
目次
映像活用が展示会にもたらす効果とメリット
展示会の現場では、限られた時間と空間の中で、いかにして来場者に訴求し、記憶に残る体験を提供できるかが重要です。その中で「映像」は、視覚と聴覚の両方に訴える強力なツールとして、多くの企業に採用されています。映像を使うことで、製品やサービスの特長を短時間で明確に伝えることができ、視覚的なインパクトを強化する効果が期待されます。
近年は、WebやSNSとの連動施策も進化しており、展示会会場での放映にとどまらず、事前告知や事後フォローにも映像を活用する流れが加速しています。こうしたマルチチャネル展開により、認知度や集客効果の最大化が可能となるのです。
また、視覚的に魅せる表現は、説明資料やパンフレットなどの静的ツールでは伝えきれない製品の動きや使用シーンなども再現可能で、来場者の理解促進にも大きく貢献します。
映像が来場者の興味を惹きつける理由
展示会では、ブースの前を通り過ぎる多数の来場者に、いかに足を止めてもらうかが最初のハードルです。その中で、映像が果たす役割は極めて大きいと言えます。
特に以下のような要素が、来場者の「興味を惹きつける」要因となります。
・ 動きのある映像表現
静止画では得られない動きがあることで、無意識に視線を引き寄せる
・ BGMやナレーションによる音声演出
音響を使ってブースの雰囲気を作り、聴覚的に注目を集める
・ テロップや字幕による情報提示
短い時間でも要点を視覚的に伝え、情報を瞬時に伝達
・ 訴求力のあるオープニングやタイトル
短時間でインパクトを与え、印象に残る映像導入を設計
また、ターゲット層の課題や関心を捉えた映像内容であれば、視聴者の感情に訴えかけ、さらに深い関心を引き出すことが可能です。映像をうまく活用することで、第一印象での差別化が実現し、ブースへの立ち寄り率が大きく向上します。
展示会で映像を使うことの具体的なメリットとは
映像には、「訴求力」と「情報伝達力」を同時に高められる利点があります。
展示会における具体的なメリットは以下のとおりです。
・ 複雑な製品・技術の説明が容易になる
テキストや口頭では伝えにくい内容を視覚的に表現することで、理解を促進
・ 短時間で多くの情報を伝えられる
限られた時間の中で製品の全体像や魅力を一気に伝えられる
・ 商談やフォローアップにも活用できる
映像を名刺交換時や後日のメールで再活用でき、営業活動の効率化にも貢献
・ ブランドや企業イメージの向上
高品質な映像を通じて、ブランドの世界観や価値観を効果的に伝達
さらに、イベント当日の人員削減にもつながるという利点があります。来場者に映像で概要を伝えることで、説明要員の人数を抑えつつ、一定の情報提供が可能になります。費用対効果の面でも、限られた予算内で最大の成果を目指す上で有効な手段と言えるでしょう。
イベントでの映像活用がもたらすブースの変化
映像の導入によって、展示ブースそのものの雰囲気や機能性にも大きな変化が現れます。
映像によって以下のようなブース演出が可能になります。
・ 視覚的に訴える空間設計
大型モニターやLEDディスプレイを組み込んだレイアウトが可能になり、会場内でも目を
引く存在に
・ 製品デモの代替・強化
実物展示が難しい大型製品や技術の説明を、動画で再現し、より具体的に訴求
・ 一貫性のあるブランド表現
映像内のデザインや色、音楽などとブース全体の構成を統一し、ブランドの印象を強化
・ 来場者の滞在時間の延長
映像をじっくり見てもらうことで、ブース内での滞在時間を自然に延ばし、商談機会の増加に
つなげる
また、映像の内容次第では、SNSで拡散されやすいインパクトある演出にもなります。ティザー的な要素を含めた映像で来場者の興味を刺激し、情報発信のツールとしても活用できる点が、現代の展示会マーケティングにおける大きな強みです。
展示会で成功するための映像演出事例
展示会における成功の鍵は、ブース設計とコンテンツ、そして映像演出の一体化にあります。単に目立つ映像を流すだけでなく、来場者の行動や興味を理解したうえでの戦略的な演出が、集客と商談数の増加を実現しています。
このセクションでは、実際の展示会で成功を収めた具体的な映像演出事例を紹介しながら、どのようにして映像が「成果」につながったのかを解説します。また、ブース設計との連動、イメージ戦略との融合といった、先進的な映像活用術についても詳しく見ていきます。
集客を最大化した映像活用事例の紹介
あるIT系企業では、新製品発表のタイミングに合わせた展示会出展にあたり、短時間で来場者の注目を集めるティザー映像を制作しました。
映像は60秒程度で、「課題提示→解決のヒント→詳細は会場で」という流れを持ち、以下のような成果を上げました。
・ ティザー映像をSNSと連動させ事前に公開
→Web上での視聴数が5万回を超え、来場動機の醸成に成功
・ ブースでは同じ映像をループ再生
→映像の音響と照明を連動させ、通行人の視線を効果的にキャッチ
・ 映像視聴者向けのノベルティ配布
→映像を観た来場者にだけ配布するキャンペーンで滞在時間が延長
結果として、前年の展示会と比較して名刺獲得数が約180%に増加。さらに、映像視聴者の約半数がその後の商談に移行するなど、集客面と営業成果の両面で大きな成果を上げました。
映像とブース設計の連動による成功パターン
映像の効果を最大化するためには、ブース設計との連動が不可欠です。単にモニターを設置するだけでは不十分で、ブース全体の動線設計や視認性、空間演出との一体感が重要です。
成功例として、ある医療機器メーカーでは以下のような工夫を施しました。
・ 巨大なLEDウォールを中央に設置
→映像がブースの「顔」として機能し、遠くからでも視認できる設計
・ 映像のテーマに合わせたカラー照明をブース全体に導入
→映像の世界観がブース全体に広がることで没入感を演出
・ 製品展示ゾーンと映像の内容を連動
→映像で紹介された製品の実物を、すぐ横に展示して導線を最適化
このように、映像と空間を一体で設計することで、視覚的な印象と来場者の体験価値が飛躍的に向上します。来場者は「このブースは印象的だった」と記憶に残し、後の商談や資料請求につながる確率が高まります。
イメージと演出が融合した映像プロモーション戦略
映像は単なる説明ツールではなく、ブランドや企業の「イメージ」を形づくる重要な表現手段でもあります。
あるグローバル企業の例では、企業メッセージと映像の演出を高度に融合させ、以下のようなプロモーション戦略を展開しました。
・ ブランドコンセプトを映像の冒頭で強く打ち出す
→「持続可能性」「人間中心のテクノロジー」といったキーワードを短く明示
・ インパクトのあるビジュアルとBGMの活用
→高速で切り替わるカット、力強い音楽、視覚的なメッセージ展開で感情に訴求
・ ストーリー仕立ての演出
→問題→課題→挑戦→解決→未来という流れで視聴者を引き込み、記憶に残る構成
この映像は展示会場だけでなく、事前のYouTube公開や事後の営業メールにも活用され、「ブランド価値の認知向上」と「営業リード獲得」を同時に達成しました。映像を「体験」として捉え、複数のチャネルで展開することで、展示会のROIを最大限に引き上げることが可能となります。
展示会映像の主な種類と使い分け
展示会において使用される映像には、実写・アニメーション・CGといったさまざまな種類があります。それぞれに特徴があり、目的や訴求対象、予算、納期に応じて使い分けることが重要です。映像のタイプを正しく選定することで、視聴者に響くメッセージを的確に届けることができ、展示会での成果向上につながります。
また、映像の種類を理解することは、制作会社への依頼時や社内での企画時に必要な判断材料となります。本章ではそれぞれの特性と活用シーンを具体的に解説しながら、展示会に適した映像表現の選び方を紹介していきます。
実写・アニメーション・CGの違いと特徴
展示会で用いられる映像は、大きく分けて以下の3種類に分類されます。それぞれの特徴を正しく理解しておくことが、効果的な表現と予算管理につながります。
| 種類 | 特徴 | 適用シーン | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 実写 | リアルな雰囲気 社員インタビューや 現場紹介に最適 |
企業紹介 インタビュー 製造プロセス紹介 |
撮影コスト 日程調整が必要 |
| アニメ | 複雑な概念も 視覚的解説 柔軟な表現が可能 |
製品仕組み紹介 SDGs訴求 |
企画構成に 時間を要する |
| CG 3DCG |
実写再現困難な 内部構造や 未来的演出が 可能 |
製品デモ ティザー広告 |
制作費高め スケジュール厳守 |
選定にあたっては、視覚的な訴求力と訴求内容の複雑さをどう両立させるかを基準に検討することが望まれます。
商品紹介に適した映像の作り方と構成
展示会での商品紹介に使用する映像は、「限られた時間で、魅力を最大限伝える構成」がカギとなります。来場者が立ち止まってくれるのはほんの数十秒から1〜2分程度。その間に興味を持たせ、製品の概要と魅力を理解してもらう必要があります。
以下のような構成で映像を作成することで、商品紹介動画として効果を発揮しやすくなります。
1. 導入(インパクトある開始)
-興味を惹くビジュアルやナレーション、BGMで視聴を促す
2. 課題提起とソリューション提示
-「どんな問題を解決する製品なのか」を明確にする
3. 製品の機能・特長紹介
-実物やアニメーション、テロップで機能や仕様をわかりやすく解説
4. 利用シーンの提案
-顧客が導入後をイメージしやすいように活用シーンを描写
5. クロージング(ブランド訴求・連絡先など)
-自社名・ロゴ・WebサイトURL・資料請求案内などの情報を明示
また、字幕やナレーション、グラフィックの工夫によって、多言語対応や視覚的な情報補完も可能です。視聴者に「この製品、気になる」と感じてもらえる構成を意識しましょう。
プロモーション動画として効果的な映像演出例
展示会におけるプロモーション映像は、単なる製品紹介とは異なり、ブランディングやコンセプト訴求の側面が強く求められます。そのため、演出や表現技法において視覚的・感情的なインパクトが重要になります。
以下は、プロモーション動画で活用される効果的な演出例です。
・ ストーリーテリング形式の構成
→実在する顧客や課題を描きながら、製品導入による「変化」を物語として伝える
・ 強烈なビジュアル表現
→カラー演出、スローモーション、BGMと同期した映像展開などで記憶に残る演出を設計
・ インタビューや実績の紹介
→実際のユーザーの声を取り入れることで、信頼性と説得力がアップ
・ ティザー形式の短尺映像
→商品の全貌を明かさず「もっと知りたい」と思わせる手法で、WebやSNSとの連動を狙う
これらの手法を用いることで、展示会場だけでなく、YouTubeや企業サイト、SNSなど他の媒体への展開も視野に入れた運用が可能となります。映像を単なる紹介ツールではなく、戦略的プロモーション資産として活用する意識が求められます。
映像機材と設置環境の最適化ポイント
映像演出に最適な機材選定は、展示会の規模や会場環境に合わせて行う必要があります。
・ プロジェクター vs. ディスプレイ
プロジェクターは大画面演出に強く、設置位置の自由度が高い一方、会場照明が強いと視認性
が低下しやすい特徴があります。高輝度ディスプレイは明るい環境でも鮮明に再生でき、
タッチパネルを用いたインタラクティブ展示も可能です。
・ LEDビジョン選定
視認距離とピクセルピッチの組み合わせを事前に検討し、遠距離/近距離どちらでも映像が
粗く見えない適切なパネルを選択します。
・ 設置計画の徹底
天井吊り下げやスタンド設置、生配線ルート、電源確保など、事前の会場調査と機材テストを
必ず実施しておきましょう。
フレッシュタウンの映像機材レンタルサービスなら、企画段階から設置当日、撤去まで一貫したサポートが可能です。詳しくは ▶︎ フレッシュタウン 映像機材レンタルサービスをご覧ください。
成果につながる映像制作のポイント
展示会で映像を活用するにあたって、最も重要なのは「成果に直結する映像制作」を行うことです。ただ目を引くだけの映像では不十分で、営業活動や出展目的の達成に貢献する映像でなければなりません。そのためには、制作前の企画設計から明確な目標設定、適切な構成と演出、そして制作実績のあるパートナー選定まで、あらゆる面において戦略的な思考が求められます。
このセクションでは、展示会で成果を出すための映像制作における重要なポイントや考え方について、具体的なアプローチを交えて解説していきます。
動画制作必須条件
来場者の注目を逃さない動画制作には、以下の条件を満たすことが重要です。
・ テロップ・グラフィック
騒音の多い展示会場でも情報を補完できるよう、大きめの文字とコントラスト強めのデザイン
を心がけます。
・ 音響設計
展示会場のBGMやナレーション、効果音は展示会の雰囲気に合わせて選定し、音量バランス
を調整して聞き取りやすくします。
・ 適切な尺設定
オフライン展示会では30~60秒、オンラインでは90秒~2分を目安に、短時間で要点を
伝えられる構成を意識します。
・ 役割分担
動画で概要を伝え、詳細は現地説明員がフォローする二段階方式を採用すると、情報提供の
効率と理解度が向上します。
映像制作の目的整理とターゲット設定
まず最初に行うべきは、映像を制作する目的の明確化です。目的があいまいなまま映像を作ってしまうと、訴求内容がブレてしまい、最終的な効果も得られにくくなります。
主な目的は以下のように整理されます。
・ 新規顧客の獲得
→視聴者が「この企業は信頼できそうだ」と感じる内容構成
・ 製品・サービスの理解促進
→分かりやすさ、視覚的な説明重視の演出や構成
・ ブランドイメージの訴求
→コンセプトや企業理念を表現した印象的な演出とBGM
・ 商談化への誘導
→問い合わせや資料請求など、行動を促すクロージングの挿入
また、ターゲットとなる来場者の属性をしっかりと想定することも欠かせません。業種・職種・課題意識・興味関心などを分析し、「誰に・何を・どう伝えるか」を明確にすることで、より響く映像表現が可能になります。社内外の関係者との合意形成を図る際にも、この目的整理は大いに役立ちます。
効果的な映像の構成と時間配分の考え方
展示会の映像は、一般的な企業紹介動画とは異なり、短時間での訴求力が求められます。来場者は複数のブースを回るため、長尺の映像をじっくり観るケースはまれです。そのため、最も伝えたいポイントを前半に配置する構成が基本となります。
おすすめの構成例は以下の通りです。
1. 0〜10秒:注目を集めるインパクトある導入
→映像全体の視聴継続率を左右する重要なパート
2. 10〜30秒:課題提起と解決策の提示
→自社の製品やサービスが「なぜ必要なのか」を明確にする
3. 30〜60秒:機能や活用シーンの紹介
→実写やCG、アニメーションでビジュアル訴求
4. 60〜90秒:事例紹介・成果・お客様の声
→信頼性の補強と訴求力の向上
5. 90〜120秒:クロージングメッセージと行動喚起
→連絡先やWebサイト、資料請求などの導線を設置
時間配分の目安は全体で90秒~2分程度が理想です。長すぎる映像は途中で離脱される可能性が高いため、目的とターゲットに即したシーンの取捨選択が求められます。
営業や出展の成果につながる動画制作の実績
実際に営業や展示会で成果を出している企業の多くは、映像制作において一定のノウハウを持つ制作会社と連携しています。特に、BtoB向け展示会では、単に美しい映像よりも「伝えるべき情報を整理し、視覚的にわかりやすく伝える」ことが重視されます。
成果につながった動画の共通点は以下の通りです。
・ 出展目的に即したストーリー設計
→自社が伝えたい情報と視聴者が知りたい情報のバランスを取った構成
・ 実績を視覚化する演出
→数値実績や顧客インタビューを用いた説得力ある内容展開
・ 映像公開後の営業活動へのスムーズな連携
→映像リンクを営業メールに添付、商談時にタブレットで再生するなどの工夫
加えて、展示会後の活用を見据えて設計されている点も見逃せません。動画は単発のコンテンツではなく、SNSやYouTube、Webサイトでの展開も前提に置いた制作が、結果としてROI向上につながっています。
映像制作会社に依頼する際の注意点
展示会で成果を出す映像を制作するためには、自社内での対応には限界があるのが現実です。撮影、編集、演出、ナレーション、音響、CG制作など、専門的な技術と機材が必要な作業が多く発生するため、プロの映像制作会社への依頼が一般的です。
しかし、制作会社を選ぶ際には注意点がいくつもあります。費用だけで選んでしまうと、期待していたクオリティに達しない、目的に合っていない映像になってしまうことも少なくありません。本章では、制作会社に依頼する際に意識すべきポイントや選定基準、確認すべき実績などを詳しく解説します。
制作費用の相場と費用対効果の考え方
映像制作の費用は、制作内容や構成、演出方法、撮影の有無、ナレーションやCGの使用などによって大きく変動します。以下はあくまで参考ですが、展示会向けの映像制作における一般的な相場です。
| 映像の種類 | 参考価格帯 | 内容例 |
|---|---|---|
| シンプルなアニメーション (1~2分) |
20〜50万円 | イラストベースの説明動画 |
| 実写撮影+編集 (1~3分) |
50〜100万円 | 撮影1日、ナレーション付き |
| CGや3DCGを含む映像 | 80〜 200万円以上 |
高度な表現を含む プロモーション |
費用対効果を検討する際には、「集客数」「名刺交換件数」「商談化率」「動画再生回数」などをKPIとして設定し、投資金額と照らし合わせて判断することが大切です。また、WebやSNSへの2次利用も視野に入れた設計を行うことで、映像の価値を最大化できます。
制作会社の選び方と依頼時のチェックポイント
適切な制作会社を選ぶためには、単に「映像が作れる」というだけでなく、展示会で成果を出すためのノウハウを持っているかどうかを見極める必要があります。
以下のような視点で比較・検討することをおすすめします。
1. 展示会向け映像の実績があるか
同業種の実績があると、製品や市場に対する理解が早い
2. 企画力・提案力があるか
漠然としたイメージでも形にしてくれるクリエイティブ力があるか
3. 制作体制と対応スピード
担当者の対応が迅速か、納期の調整が可能かなども重要
4. 著作権・使用許諾の明確さ
BGMやナレーションの使用範囲、納品後の利用条件を事前に確認
また、依頼前には「自社の目的や想定しているイメージを具体的に伝える準備」も必要です。ナレーションの要否や字幕の有無、動画の長さ、再生環境(会場のスクリーンやモニターサイズ)なども、制作会社に明示しておくことで、認識のズレを防げます。
映像制作を依頼する際に確認すべき制作実績
制作会社の実力を見極めるうえで、過去の制作実績を確認することは必須です。
以下のような観点でチェックしましょう。
・ 展示会向けの制作実績が豊富か
→専門性や目的理解度に差が出る
・ 類似業種・製品の映像を制作しているか
→自社のターゲットやメッセージに近い制作経験があると安心
・ 映像の完成度とメッセージの一貫性
→視覚表現だけでなく、訴求内容の設計が優れているかを確認
加えて、「この映像でどれだけの反響や成果があったか」といった活用事例や成果データを提示してもらえる制作会社であれば、より信頼性が高いと言えるでしょう。
なお、見積もりを複数社から取り、比較検討することも重要です。価格だけでなく、提案内容・納期・対応品質など、総合的に判断して選定を行うことが、後悔のない映像制作につながります。
フレッシュタウンの映像制作サービス
弊社フレッシュタウンでは、企画設計から撮影・編集、会場での機材設置サポートまで一貫して対応可能です。
・ 企画設計:展示会目的に合わせたストーリーボード作成
・ 撮影・編集:実写・CG・アニメーションを組み合わせた高品質制作
・ 会場サポート:機材選定・設営から当日の運用までフルサポート
・ 二次活用支援:展示会後のWeb公開やSNS連動配信までご提案
弊社で制作した展示会出展時に活用するための動画事例をいくつかご紹介させていただきます。
▶展示会動画事例1:ATIRO株式会社様
▶展示会動画事例1:日建塗装工業株式会社様
▶展示会動画事例1:株式会社MAENI様
もし、ご興味をいただきましたら、ぜひ下記ボタンよりお問い合わせくださいませ。出展計画に合わせた制作のポイントやプランニングを行います。
まとめ:映像を活用した展示会は成果につながる
展示会での映像活用は、ただの演出にとどまらず、企業の目的達成に直結するマーケティング戦略の一環として機能します。映像を用いることで、来場者の関心を引き、限られた時間の中でも高い情報伝達力を発揮し、商談や顧客獲得に繋がる成果を生むことができます。
以下に本記事の要点をまとめます。
☞展示会における映像活用は、集客・訴求・成果を最大化する強力な武器
1. 映像は来場者の注目を集め、短時間で情報を伝達できる強力なツール
・ 動きと音の組み合わせにより視覚・聴覚に訴え、印象に残るブース演出を実現
2. 映像には用途や目的に応じた種類と作り方がある
・ 実写・アニメーション・CGを使い分け、ターゲットや製品内容に最適化された表現を
採用
3. 成果を出す映像には明確な目的設定と構成が必要
・ ターゲットを意識し、短時間でも内容が伝わる構成を意識することで効果を発揮
4. 制作会社の選定と費用のバランスも成果に影響
・ 実績と提案力を兼ね備えた会社選びが重要。コストだけでなく内容を重視
5. 成功事例に学び、映像とブースを一体で設計することが鍵
・ 集客に成功した企業の多くは、映像と空間を連動させた体験型プロモーションを実施
展示会の現場では、「伝わるかどうか」ではなく「伝える工夫があるかどうか」が勝敗を分けます。映像はその最前線を担うツールとして、戦略的に設計・運用されることで真の効果を発揮します。来場者の心に残るブースを作りたいなら、映像を最大限に活用することが不可欠です。
Q&A
展示会用の映像はどのくらいの長さが適切ですか?
来場者の滞在時間を考慮すると、60秒〜120秒程度の短時間映像が効果的です。長尺映像は離脱の原因となるため、内容をコンパクトにまとめ、再生環境(画面サイズや音響)とのバランスも意識しましょう。
映像制作の料金プランはどう決めれば良いですか?
まずは目的・表現方法・再生環境を整理し、それに応じた制作内容(実写、CG、ナレーション、テロップの有無など)を明確にします。そのうえで制作会社に複数のプランを見積もり依頼し、費用対効果を比較検討するとよいでしょう。
展示会映像はWebやSNSにも使えますか?
はい、活用可能です。WebサイトやSNSでの事前公開や事後フォローにも展開することで、展示会当日以外の場面でもブランド訴求や見込み顧客への接触機会を広げることができます。企画段階からマルチチャネル展開を見据えた構成にすると効率的です。
映像の制作期間はどのくらい見ておくべきですか?
一般的には1〜2か月の制作期間を見込むのが安全です。構成の確認、撮影日程の調整、編集やナレーション収録、確認・修正対応など複数工程があるため、余裕を持ったスケジュール設計が重要です。納品前に試写する時間の確保も忘れずに。
映像制作を社内だけで行うことは可能ですか?
簡易的な編集や素材の流用であれば社内でも可能ですが、映像のクオリティや集客成果を重視する場合は外部の専門制作会社の活用が推奨されます。特に展示会用の映像は視覚・音響・演出面で高い完成度が求められるため、経験豊富なパートナーとの連携が重要です。