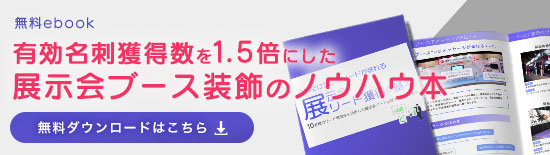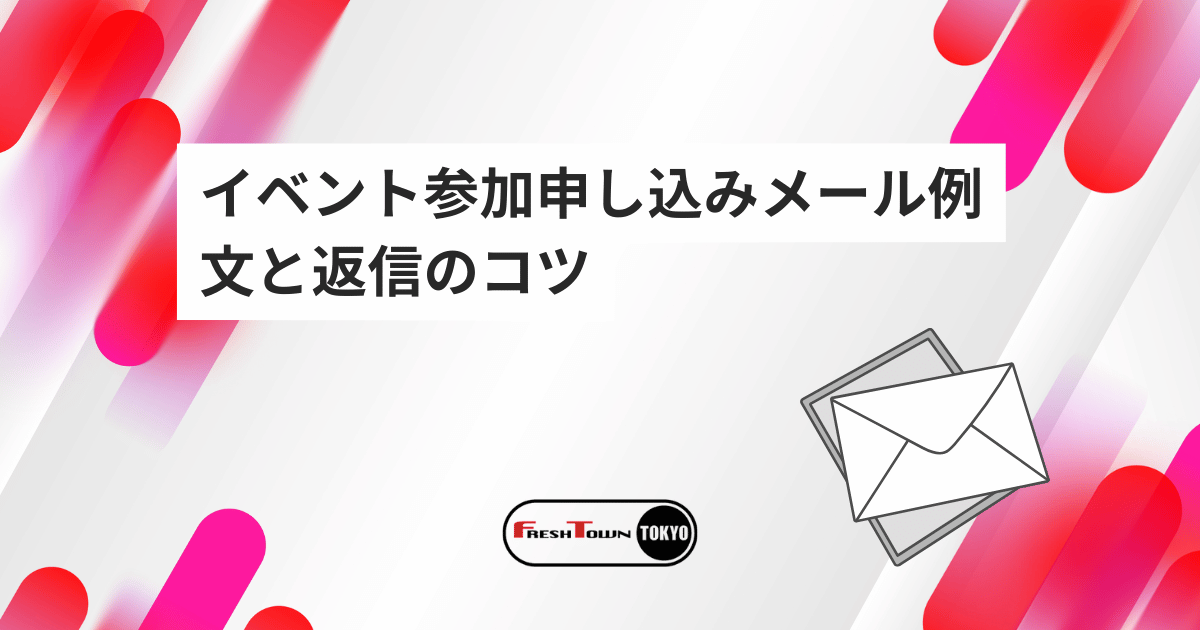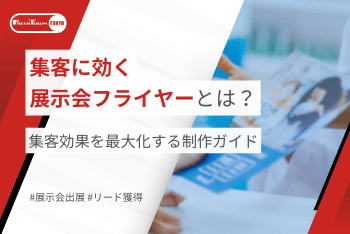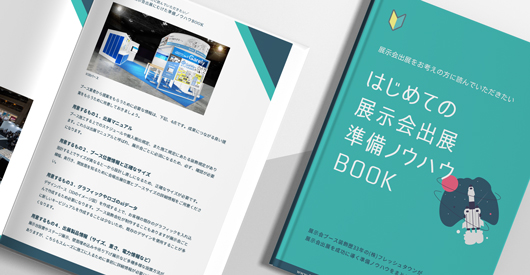展示会で差がつくパンフレットの種類と活用法
INDEX

展示会において、パンフレットは自社や製品の魅力を伝えるための重要なツールです。来場者がブースに立ち寄るかどうか、またどれだけ印象に残るかは、パンフレットの出来栄えに大きく左右されます。ただ配布するだけでは意味がなく、ターゲットに合わせた内容構成、見やすく魅力的なデザイン、コンパクトかつ効果的な情報整理が求められます。
本記事では、展示会で活用されるパンフレットの種類や特徴を比較し、効果的に来場者の関心を引くための具体的な作り方や工夫を解説します。会社案内やイベント資料といった用途別の制作方法、実際の成功事例を交えながら、展示会で「選ばれるブース」になるための秘訣を紹介します。
パンフレットの基本:展示会での役割と目的
展示会におけるパンフレットの役割は、単なる配布物にとどまらず、企業の魅力や製品の訴求ポイントを来場者に的確に伝えるための情報ツールです。来場者が短時間で企業の全体像を把握し、興味を持つための「入口」となるため、その構成やデザインは極めて重要です。
パンフレットを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
・ 自社の製品やサービスを簡潔に伝えられる
・ 来場者が持ち帰って再確認できる情報源になる
・ ブースに立ち寄らなかった人にも情報提供が可能
・ 商談のきっかけや後日連絡の材料として活用できる
また、資料としての整理性、視覚的なインパクト、手に取りやすいサイズなど、会場での行動導線を想定した工夫も重要です。展示会の開催目的やターゲットに応じて、パンフレットの内容と仕様を最適化することが、ブース全体の成果につながります。
来場者に与える第一印象とパンフレットの重要性
展示会では、限られた時間と空間の中で、いかに「記憶に残る」かが成功のカギとなります。来場者の多くは複数のブースを回るため、一つひとつの企業や製品について深く理解するのは難しいのが実情です。そのため、第一印象で惹きつけ、資料として持ち帰りたくなるパンフレットが必要とされます。
パンフレットが与える第一印象には以下の要素が関係します。
・ 表紙デザインのインパクト:色使いや写真、キャッチコピーの工夫が鍵
・ コンテンツ構成の明快さ:製品紹介や実績、事例などが簡潔に整理されているか
・ 紙質・印刷の品質:信頼性やブランドイメージを左右する要素
・ イラストや画像の使い方:複雑な説明も視覚的に理解しやすくなる
さらに、パンフレットに動画へのリンクやQRコードを追加することで、Webサイトやオンラインカタログとの連携も可能です。これにより、会場外でも追加情報にアクセスできる導線が作られ、展示会の効果が持続します。
種類別に見るパンフレットの特徴と選び方
展示会で使用されるパンフレットにはさまざまな種類があり、用途やターゲットに応じて最適なものを選ぶことが大切です。
主なタイプには以下のようなものがあります。
・ 三つ折りタイプ:コンパクトながら情報量を確保でき、会場での配布に便利
・ 中綴じ冊子タイプ:ストーリー性や詳細な情報が求められる会社案内や製品資料に最適
・ 一枚もののリーフレット:伝えたいポイントを絞って訴求する場面に効果的
パンフレットの種類選定にあたっては、目的や配布シーン、情報量、印刷コストなどを踏まえることが重要です。例えば、商品数が多いカタログ形式での紹介を目的とするなら中綴じが適しており、逆に導入ツールや初回配布用としては三つ折りが効果的です。
さらに、予算との兼ね合いで印刷方法や用紙の質感も調整が可能です。大量に配布する予定であれば、簡易印刷を活用することでコストを抑える一方、限定的に渡すパンフレットには高級感のある紙質を選ぶことで差別化を図ることもできます。
三つ折り・中綴じ・一枚もの…タイプ別メリットと印刷のポイント
各タイプには独自のメリットがあり、印刷の際には以下の点に注意することで仕上がりや効果が変わってきます。
三つ折りパンフレット
・ 持ち運びやすく、展示会での配布ツールとして重宝
・ 導線を意識したレイアウト設計が必要
・ CTA(行動喚起)やQRコードの配置も重要な要素
中綴じ冊子パンフレット
・ 会社案内やサービス紹介など、情報を深掘りしたい場合に最適
・ 写真やイラストを多用することで視覚的な理解をサポート
・ 表紙と裏表紙のブランディング強化がしやすい
一枚もののリーフレット
・ 限定キャンペーンや店舗誘導など、明確な目的で活用
・ 両面を活用して情報を整理することで、読みやすさを向上
・ 他社との差別化を図るためには、用紙選びと印刷加工が鍵
印刷においては、「用紙の厚み」「光沢の有無」「印刷色数」なども重要な判断材料になります。パンフレットの「作り方」に関する基本的な知識と、成果につながる見せ方のコツを押さえることが、展示会での成果向上につながります。
ターゲット別に最適なパンフレットの作成法
展示会で効果的なパンフレットを作成するには、あらかじめ明確にターゲットを設定し、そのニーズに合わせた情報を届けることが重要です。来場者は多様な背景や関心を持っており、汎用的な資料では印象に残りづらくなります。
ターゲットを意識したパンフレット制作の基本ステップは以下の通りです。
・ ターゲット層の分類(例:導入を検討する担当者、意思決定者、技術職など)
・ 役割に応じた情報設計(製品機能重視、価格重視、実績重視など)
・ 想定シナリオに基づく構成(導入前・導入中・導入後の流れを想定)
特にBtoBの展示会では、「決裁者向け」「現場担当者向け」といったパンフレットを複数種類用意しておくことが効果的です。それぞれの層に刺さるメッセージや事例、コスト効果を明示することで、商談の質を高めることができます。
また、来場者の興味を引くには、単なる製品説明ではなく「何が解決できるか」という課題解決型の訴求が求められます。
自社製品と来場者層を意識した情報設計のコツ
ターゲットに響くパンフレットを作るためには、自社の製品特性や導入実績を踏まえた具体的な情報設計が欠かせません。
以下のような工夫を取り入れると効果的です。
・ ビジュアルで魅せる:製品の使用シーンや効果を伝える画像や図解を活用
・ 課題ベースの構成:来場者の「悩み」に寄り添ったストーリー設計
・ CTAの明確化:資料請求、商談予約、Webサイトへの誘導など次の行動を明示
・ 簡潔な説明と視線誘導:余白や文字サイズ、色使いで読みやすさを向上
さらに、実際の導入事例やお客様の声を掲載することで、信頼性や説得力が増します。可能であれば、展示会限定の特典やオファーを記載することで、即時の反応を引き出しやすくなります。
ターゲットに合わせて内容を調整したパンフレットは、情報の「伝達力」だけでなく、「記憶に残る力」も高くなり、展示会終了後のフォローアップにもつながります。
デザインと表紙の工夫で印象を差別化する方法
パンフレットのデザインは、展示会における来場者の足を止めるための大きな要素です。中でも、表紙は「開かせる力」を持つ非常に重要な部分です。表紙の印象で読み手の関心が決まるため、他社との差別化を図るためにも、視覚的な演出やブランドイメージに配慮したデザインが求められます。
以下のような点を押さえることで、印象的なパンフレットのデザインに近づけます。
・ ブランドカラーの一貫性を持たせることで、企業の統一感をアピール
・ ロゴやキャッチコピーを目立つ位置に配置し、印象を強める
・ 写真やイラストの高解像度素材を使用し、視覚的な質感を演出
・ レイアウトと構成を整理し、見やすく読みやすい配置にする
また、配布用パンフレットの場合、来場者が鞄に入れやすいサイズ感や形状も重要です。デザインだけでなく、手に取ったときの扱いやすさ、折りやすさなどの物理的な配慮も評価ポイントとなります。
配色・レイアウト・キャッチコピーでブースに足を止めさせる秘訣
展示会会場では、数多くのブースが立ち並ぶ中で、ひと目で「違い」を感じさせる工夫が必要です。パンフレットのデザインもそのひとつとして、ブースの「顔」となる役割を担います。特に、配色やキャッチコピーは「直感的な興味」を引くために非常に効果的です。
効果を高めるためのデザイン上のポイントは以下の通りです。
・ 配色:企業カラーをベースにしつつ、補色やアクセントカラーで視線を誘導
・ キャッチコピー:ターゲットの悩みに直結する一文を大胆に配置
・ 視線誘導:Z型・F型レイアウトを意識し、自然に情報を読ませる工夫
・ 余白の活用:情報を詰め込みすぎず、空間で見やすさを保つ
・ 表紙写真の選定:製品や導入シーンが明確に伝わる写真を使う
また、フォントの選定や見出しのサイズ、装飾の加減など、細部にも配慮することでパンフレット全体の完成度が向上します。来場者の視界に自然に入る「訴求力」を持ったデザインが、来場→関心→資料持ち帰り→商談化の導線を生み出します。
成功事例から学ぶ効果的なパンフレット活用術
展示会でパンフレットを活用する際、ただ配布するだけではなく、戦略的な使い方が求められます。パンフレットは営業トークの補助資料であり、来場者の記憶に残すツールであり、後日のアプローチを助ける販促媒体でもあります。
ここでは、実際の展示会で成果を上げた企業の事例から学ぶ、パンフレットの効果的な活用法をご紹介します。
実際の展示会での配布タイミングとツール連携方法
あるITソリューション企業では、以下のような工夫を実施し、商談化率を大幅に向上させることに成功しました。
1.タイミングを見極めた配布
・ ブースの説明後に渡すことで、理解が深まった状態で持ち帰ってもらう
・ 興味が薄そうな来場者にも会話のきっかけとして活用
・ プレゼンやデモ後に手渡すことで、印象の定着を促進
2.他ツールとの連携
・ パンフレット内に動画リンクやQRコードを設置し、製品デモやWebサイトへ誘導
・ 名刺管理アプリやCRMツールと連動し、配布記録や反応をデータ化
・ SNSキャンペーンやメールマガジンと連動し、事後のフォローを強化
3.チームで役割分担
・ スタッフがパンフレットの内容を熟知し、説明と連携して活用
・ 担当者の情報を記載したパンフレットで、信頼性と問い合わせ導線を確保
また、ある製造業の出展企業は、「来場者の課題別パンフレット」を3パターン用意し、来場者の反応に応じて最適な資料を配布するスタイルを採用。これにより、来場者の関心に即した提案が可能になり、商談の成立率が倍増しました。
効果的な活用には、配布だけにとどまらない工夫と、他ツールとの連携設計が鍵となります。事前準備、当日の対応、事後フォローまでを見据えた設計が、パンフレットの成果を最大化させるのです。
展示会当日の名刺交換・トーク・資料配布のコツと注意点について詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会成功のカギは説明員|事前準備から当日まで徹底解説も是非ご一読ください。
まとめ:展示会パンフレットで差をつけるために必要なこと
展示会で成果を上げるには、パンフレットの質と戦略的な活用が不可欠です。見た目やデザインだけでなく、「誰に、何を、どう伝えるか」を明確にし、準備から配布、そしてその後のフォローまでを一貫して設計することで、パンフレットは単なる配布物ではなく、商談を生み出す強力なツールになります。
☞展示会パンフレット成功のための重要ポイント
1. ターゲットを意識した設計
・ 来場者層に応じた内容やレイアウトを構成し、それぞれの関心や悩みに寄り添う
資料を用意
2. 用途に合った種類の選定
・ 三つ折りや中綴じ、一枚ものなど、目的や情報量に応じた最適なタイプを選ぶことで
配布効果を最大化
3. 第一印象を左右するデザインと表紙
・ 表紙のインパクトやキャッチコピーで目を引き、ブースに足を止めてもらう工夫が必要
4. 他ツールとの連携と配布タイミングの工夫
・ QRコード、Webサイト連携、名刺管理など、配布後の行動につながる仕掛けを
組み込む
5. 成功事例に学ぶ具体的な工夫
・ 課題別パンフレット、担当者情報の記載、会話のきっかけづくりなど、実践的な
テクニックを応用する
6. 一貫したメッセージとブランディング
・ パンフレットの中で一貫したトーンとイメージを保つことで、企業としての信頼性と
記憶定着を高める
パンフレットは「資料」ではなく、「展示会成果を左右する営業ツール」です。事前の企画段階から綿密に計画し、来場者の記憶に残るような設計と演出を心がけることが、他社に差をつけるカギとなります。
お役立ち資料
CASE STUDY
創業以来培ったノウハウとデータをもとにまとめたハンドブックです。
「初めての展示会で何をやったら良いかわからない」「効率的に成果を出すブースづくりについて知りたい」、そんな方におすすめです。
本資料は展示会出展社さま、展示会出展をご検討されている方に向けて作成した資料です。 同業他社さまには資料ダウンロードをご遠慮いただいております。申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。