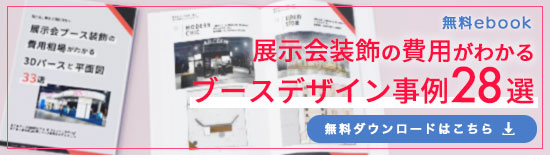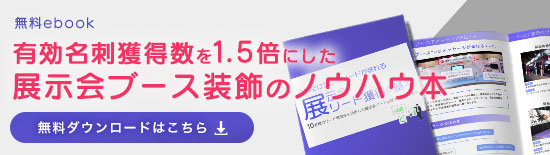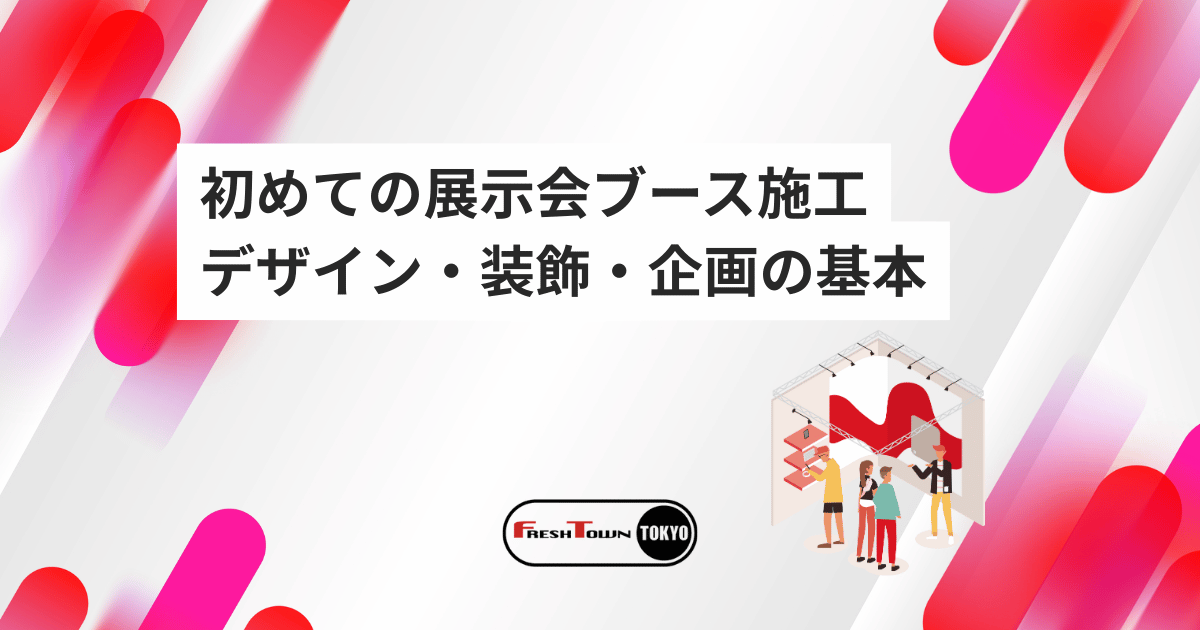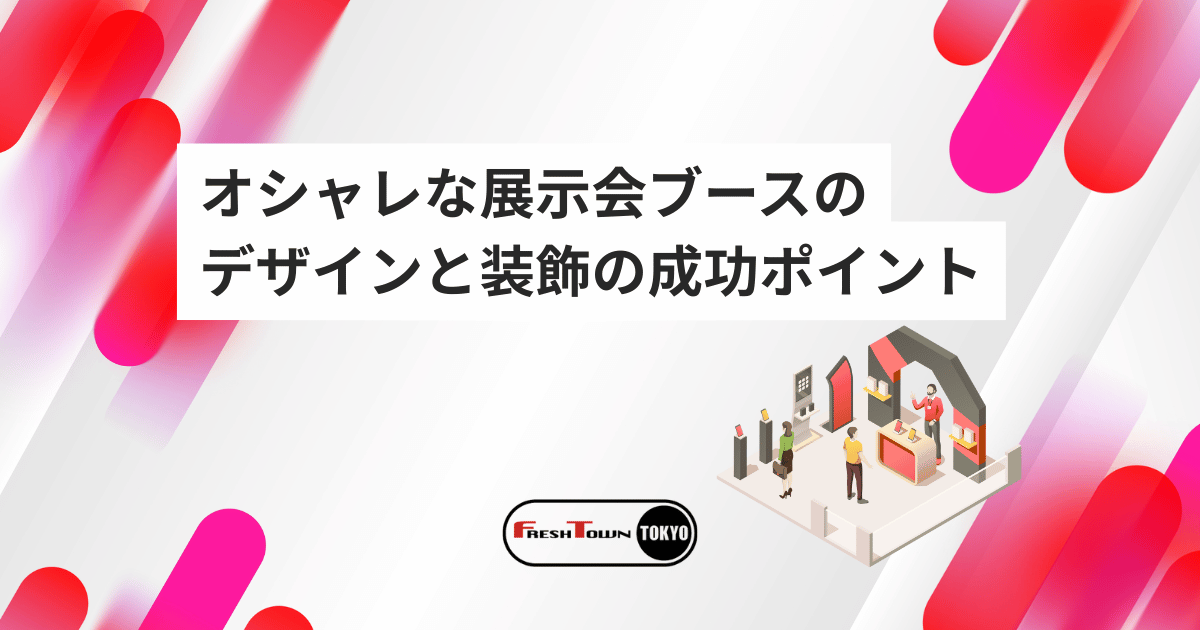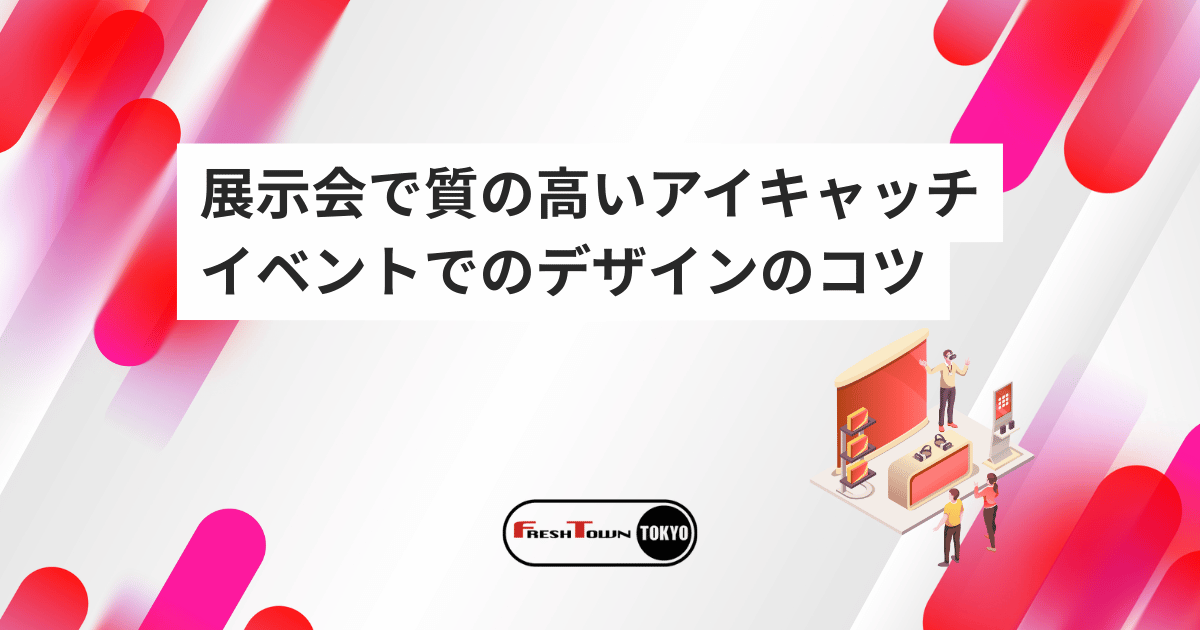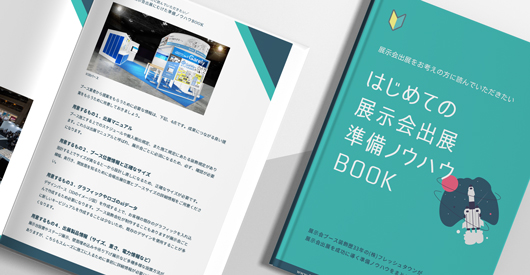展示会装飾の基本を徹底解説!出展成果につなげる装飾とは
INDEX

展示会は、企業が製品やサービスをアピールするための重要な場です。その中でも、装飾やブースデザインは、来場者の目を引き、印象を残すために欠かせない要素です。限られたスペースの中でどのようにブランドを訴求するか、どうすれば集客につながる導線やレイアウトを設計できるかが、成功の鍵を握ります。
本記事では、展示会における装飾の基本的な考え方から、ブース設計のコツ、さらには装飾アイテムの選び方や業者への依頼方法までを、実践的な観点から詳しく解説します。加えて、実際の事例を交えながら、効果的な設計や費用対効果の高い演出方法についても触れていきます。
「初めて展示会に出展する方」や「より効果的な展示を目指す企業担当者」にとって、明日からの準備にすぐ役立つ情報を提供します。ぜひ最後までお読みいただき、展示会での成功にお役立てください。
展示会装飾の基礎知識と重要性
展示会での装飾は、単なる見た目の演出ではなく、企業のメッセージやブランド価値を伝える重要な手段です。限られたスペースの中で最大限の効果を生み出すには、目的に沿った設計と明確なターゲティングが不可欠です。
装飾における基本的なポイントは以下の通りです。
・ 来場者にとってわかりやすく、興味を引くレイアウト
・ 製品やサービスの魅力を端的に伝えるパネルやバナーの活用
・ 商談や説明がしやすいテーブルや椅子の配置
・ 会場全体の雰囲気と調和した色使いと演出
これらを総合的に考慮することで、展示会ブースは単なる空間から、訪れた人の心に残る「伝える場」へと進化します。
展示会における装飾の役割と目的
装飾の主な役割は、出展企業のブランドや製品の印象を高めることにあります。ただのデコレーションではなく、「何を」「誰に」伝えるのかを明確にした企画と設計が求められます。
以下のような目的に応じて装飾を最適化することが重要です。
・ ターゲットの注目を集めるための訴求力あるデザイン
・ ブランドイメージを強調する統一感のある色や素材の選定
・ 製品やサービスの特徴を効果的に伝える什器やディスプレイ
また、初めての来場者にも安心感を与えるようなレイアウトや、社名が明確に伝わるサイン表示も欠かせません。こうした装飾がうまく機能することで、来場者の滞在時間が伸び、商談や資料請求といった具体的なアクションへとつながります。
ブースのタイプとレイアウト設計のポイント
ブースのタイプやレイアウトの設計は、展示会での成功を左右する重要な要素です。限られたスペースをどう使うかによって、来場者の導線や商談のしやすさ、製品の訴求力が大きく変わってきます。
まずは自社の出展目的や展示する製品の種類に応じて、適したブースのタイプを選ぶ必要があります。主なタイプには以下のようなものがあります。
・ オープン型:複数方向からアクセス可能で、自由に立ち寄れる設計
・ 壁面型:背面や側面にパネルを設置して、情報を集中的に訴求
・ 個室型:プライベートな商談スペースを備えた構造
・ スタンド型:限られた広さでもインパクトを与えやすい簡易設計
これらのタイプごとに、必要な什器やアイテムも変わるため、事前のプランニングが欠かせません。
さらに、会場の構造や小間の位置、来場者の流れを意識した設計を行うことで、より効果的なアピールが可能になります。
タイプ別に事例をいくつかご紹介します。
▶ オープン型のブース装飾
・ 事例1:株式会社Leaner Technologies様
会場最大ブースとしての存在感とサービス訴求を最大限高めたシステムブースの株式会社Leaner Technologies様の事例です。
・ 事例2:東洋製罐株式会社様
新キャッチコピーに合わせて「エコ」を演出した大小間ブースの東洋製罐株式会社様の事例です。
・ 事例3:株式会社アイドマ・ホールディングス様
コーポレートカラーとリード獲得をコンセプトに、複数展示会で統一したブランディングブースの株式会社アイドマ・ホールディングス様の事例です。
▶ 壁面型のブース装飾
・ 事例4:高圧ガス工業株式会社様
展示物の見易さを極めつつ電車に見立てて細部までこだわった遊び心満載の展示ブースの高圧ガス工業株式会社様の事例です。
・ 事例5:ロンシール工業株式会社様
出展商材である床材をブースで使用。ショールームのような清潔感と高級感を演出した空間づくりのロンシール工業株式会社様の事例です。
▶ スタンド型のブース装飾
・ 事例6:株式会社BEC様
システム部材のメリットをフルに活用しブランドイメージを体現した株式会社BEC様の事例です。
出展目的に応じたブースタイプの選び方
ブースの設計は、「誰に」、「何を」、「どう見せるか」によって最適な形が異なります。以下に、目的別におすすめのブースタイプを紹介します。
認知度向上を狙う場合
・ オープン型ブースで自由に立ち寄れる雰囲気を演出
・ テーブルクロスやバナーで社名や製品を明確に表示
商談や説明を重視する場合
・ 個室型でじっくりと対応できる環境を用意
・ パネルやディスプレイで製品を詳細に解説
新製品のPRやインパクト重視の場合
・ 高さを活かしたスタンド型で遠くからの視認性を確保
・ 照明や色彩の工夫で目を引く演出を実施
選定に際しては、見積もりをしっかり取り、予算とのバランスを見ながら計画を立てることが大切です。また、設置や撤去のしやすさも考慮しておくと、会期中やその後の対応がスムーズになります。
装飾アイテムの選定と配置の工夫
展示会ブースの魅力を最大限に引き出すためには、適切な装飾アイテムの選定と、その配置の工夫が重要です。来場者の目を引き、足を止めてもらうためには、視覚的な訴求力と動線設計を両立させることが求められます。
主な装飾アイテムとその活用方法は以下の通りです。
・ パネル:企業概要や製品の特長を伝える基本アイテム。目線の高さに設置すると効果的
・ バナー・タペストリー:視認性の高い場所に設置することで、ブースの認知性を向上
・ テーブルクロス:統一感のあるデザインでブランドイメージを補強
・ ディスプレイ什器:製品を立体的に見せるために有効。サイズや高さに工夫が必要
・ ノベルティグッズ:手に取ってもらえることで、ブランドの記憶に残るアイテム
また、照明や床材の工夫によっても雰囲気は大きく変わります。特に空間全体の印象を左右する要素として、細部まで意識することが成功のカギになります。
集客につながるアイテムと配置のポイント
単に装飾するだけでは、効果的な集客にはつながりません。以下のポイントを押さえて、戦略的に装飾アイテムを選び、配置しましょう。
1. 目を引く位置にアイキャッチアイテムを設置
・ 入り口付近や人の流れが多いエリアにスタンドバナーを配置
・ 高さのあるアイテムは遠方からの視認性が高くなる
2. 滞在時間を伸ばすアイテムの導入
・ 体験型のディスプレイやサンプル配布コーナーを設置
・ 手に取りやすく、興味を持たせるツールを活用
3. 商談に繋げるための資料設置と誘導導線
・ テーブルの上にわかりやすいパンフレットをセット
・ 什器を使って動線をナビゲートし、スムーズな流れを演出
4. デジタルツールの活用
・ QRコードやタブレット端末で情報提供や問合せを簡単に
・ その場で資料請求や見積もり依頼ができる仕組みも効果的
こうした工夫により、見た目の良さだけでなく、商談やリード獲得といった実際の成果にもつながるブース運営が可能となります。
装飾業者の選び方と依頼時の注意点
展示会の成功において、装飾業者の選定は非常に重要な工程です。良質な業者に依頼することで、限られた予算や納期の中でもクオリティの高いブースが実現できます。一方で、業者選びを誤ると、トラブルや追加費用の発生、納品遅延などリスクも伴います。
装飾業者を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
・ 過去の実績が豊富で、同業種や同規模の対応経験があるか
・ 提案力や対応力があり、こちらの意図を正確に理解してくれるか
・ 見積もりやスケジュールが明確で、納期を厳守できるか
・ 設営から撤去までワンストップで依頼できるか
・ 所在地が近く、会場対応にフットワーク軽く動けるか
また、業者によっては、オリジナルのパッケージプランや無料のデザイン支援を行っているケースもあるため、複数社に問合せをして比較することが大切です。
実績・対応力・費用の比較ポイント
業者選定では、「安いから」という理由だけで判断するのは危険です。以下のような観点で、総合的に比較・評価を行いましょう。
1. 実績と専門性の確認
・ 同業界での展示会施工経験があるか
・ デザインの質や納品実績が確認できるか(ポートフォリオ)
2. 提案内容のわかりやすさと柔軟性
・ 希望に対して柔軟な対応ができるか
・ レイアウト変更や追加アイテムへのスムーズな対応
3. 費用と見積もりの内訳
・ 含まれている作業範囲(設置・撤去・運搬など)が明確か
・ 追加コストが発生しないか、キャンセル規定はどうか
4. アフター対応の有無
・ 展示会終了後のフォローや保守対応があるか
・ 次回出展に向けた改善提案がもらえるか
信頼できる業者は、単なる「施工」だけではなく、企業の目的を理解したうえで、成果を意識したブースづくりをサポートしてくれます。
装飾会社の選び方について詳しく解説している記事もご紹介します。 展示会の装飾会社選びのポイント|展示会の業者タイプと業者選びで知っておくべきことも是非ご一読ください。
設営・施工から納品までの流れを解説
展示会における装飾は、企画段階から納品・撤去まで一連のプロセスをしっかり管理することが求められます。とくに施工や設営は、当日のトラブルを避けるためにも、事前準備を念入りに行うことが不可欠です。
以下は、一般的な展示会装飾における準備から完了までの主な流れです。
1. 企画・ヒアリング
・ 出展目的やターゲット、会場条件の確認
・ 必要なアイテムや展示内容のすり合わせ
2. デザイン・設計
・ レイアウトやブース構造、パースの作成
・ 使用する素材や色彩、演出手法の決定
3. 見積もり・発注
・ 費用の内訳確認と予算調整
・ 納期の確認と正式な制作依頼
4. 製作・準備
・ パネルや什器などの製作
・ 印刷物やノベルティの入稿・手配
5. 設営・搬入
・ 会期直前に会場でブースの設営・設置を実施
・ 電源・インフラなどの最終確認
6. 撤去・フォロー
・ 会期終了後に速やかな撤去・片付け
・ 機材返却やデータ整理、次回出展への改善フィードバック
このように、展示会の装飾は単なる施工ではなく、綿密なスケジューリングと各工程での確認作業が重要です。
展示会までに押さえるべき準備工程
スムーズな展示会運営のためには、次のような準備を段階的に進めることがポイントです。
1. 3カ月前:全体計画と業者選定
・ 会場予約と出展内容の決定
・ 業者への見積もり依頼と比較・選定
2. 2カ月前:ブース設計と製作手配
・ パネルや什器のデザイン確定と入稿
・ ノベルティや配布資料の準備
3. 1カ月前:設営シミュレーションと最終調整
・ 必要備品の手配と搬入スケジュール作成
・ スタッフの配置や当日の流れの確認
4. 会期直前:搬入・設営・チェック
・ ブース設営、表示内容や導線の最終確認
・ 受付時間や当日の運営フローの共有
事前の準備をしっかり行うことで、展示会当日のトラブルを最小限に抑え、最大限の効果を得ることができます。
展示会出展の準備について詳しく解説している記事もご紹介します。 展示会出展の準備とスケジュールを徹底解説!事前準備で出展成功へも是非ご一読ください。
アフター対応と次回への支援について
展示会は当日の運営で終わりではありません。出展後のアフター対応が、その成果を長期的に活かすための鍵となります。名刺交換や問合せへの対応、社内報告や次回出展の企画など、戦略的なフォローアップを行うことで、顧客との関係性を強化できます。
とくにBtoB分野では、展示会で得たデータや反応を分析し、次にどう繋げていくかが重要です。以下のような施策がアフター対応として効果的です。
・ 名刺管理システムへの登録と分類
・ 反応の良かったアイテムや導線の振り返り
・ フォローアップメールや営業訪問による継続接点づくり
・ 社内共有用のレポート作成と効果測定
これらを確実に行うことで、展示会の投資対効果(ROI)を高めると同時に、次回の出展にもつながる改善点を抽出できます。
アフターフォローで得られるメリットとは
出展後の支援やアフター施策を怠らないことは、単発のPRに留まらず、企業全体のマーケティング活動に好循環をもたらします。
主なメリットは以下の通りです。
・ 商談化率の向上
フォローの早さが信頼に直結し、成約に繋がる可能性が高まる
・ 次回展示会の改善材料を得られる
スタッフや来場者からの質問を集計し、次の訴求ポイントに反映
・ 顧客情報の精度向上
名刺やアンケートを整理・分析することで、ターゲットの精度が高まる
・ プロモーション戦略の再構築
展示会の反応をもとに、デジタル施策との連動を強化できる
・ 自社強みの可視化
成功したポイントを社内で共有し、組織全体のノウハウとして蓄積
また、信頼できる業者の中には、アフター対応まで一括でサポートしてくれるところもあります。ツールの提供や改善提案を含め、長期的な視点での協力体制を築くことが、継続的な成功への近道です。
展示会後のフォローについて詳しく解説している記事もご紹介します。 展示会後のフォローを成功させる方法とは?|フォローから商談獲得も是非ご一読ください。
まとめ:展示会装飾で成功するために必要な視点
■展示会は、装飾と設計の工夫次第で成果が大きく変わるビジネスチャンスの場
展示会装飾は、単なる装飾作業ではなく、企業の目的やターゲットに沿った戦略的な施策です。来場者に伝えたいメッセージを明確にし、それを視覚的・体験的に伝えることで、記憶に残る出展となります。
☞展示会成功のための重要ポイント
1. 目的の明確化と全体設計の整合性
・ 出展の目的(新規リード獲得、認知向上など)を明確にし、それに沿ったデザイン
や配置を行う
2. ターゲットに響くブースデザイン
・ 製品・サービスの魅力を伝えるために、パネルや什器、演出を効果的に組み合わせる
3. 装飾アイテムの選定と配置の最適化
・ スペースに応じたアイテムを選定し、動線設計と見せ方を工夫することで集客効果を
最大化
4. 業者との連携によるスムーズな準備と設営
・ 実績ある業者と連携し、見積もりや納期、アフター支援まで一貫した対応を依頼
5. 展示会後のアフターフォロー
・ 名刺管理、来場者対応、資料送付などを迅速に行い、商談や次回出展への活用に
つなげる
6. 効果測定と改善サイクルの構築
・ データ分析を通じて成果を可視化し、PDCAを回してより効果的な出展へとつなげる
限られた会期の中で成果を出すには、単なる装飾だけでなく、準備・実施・フォローまで一貫した戦略が必要です。本記事を通じて、自社に合った展示会戦略を再考し、次の出展での成功をぜひ実現してください。
お役立ち資料
CASE STUDY
創業以来培ったノウハウとデータをもとにまとめたハンドブックです。
「初めての展示会で何をやったら良いかわからない」「効率的に成果を出すブースづくりについて知りたい」、そんな方におすすめです。
本資料は展示会出展社さま、展示会出展をご検討されている方に向けて作成した資料です。 同業他社さまには資料ダウンロードをご遠慮いただいております。申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。