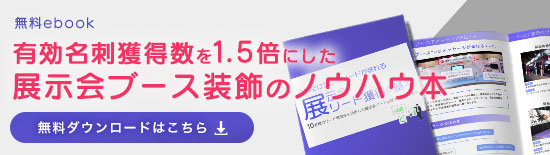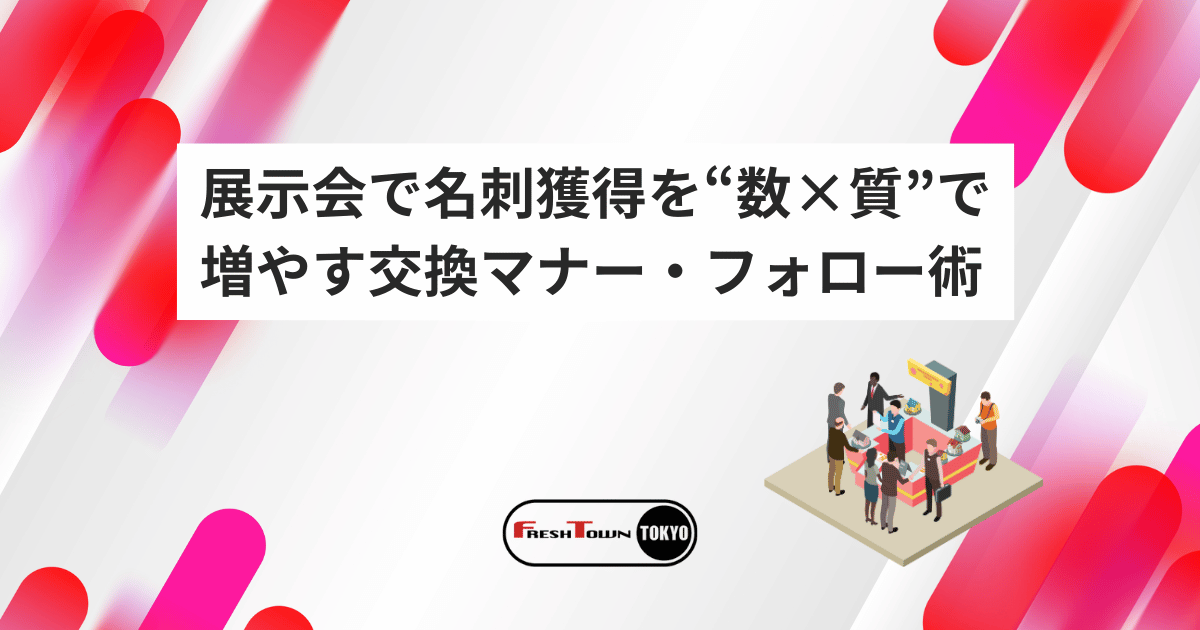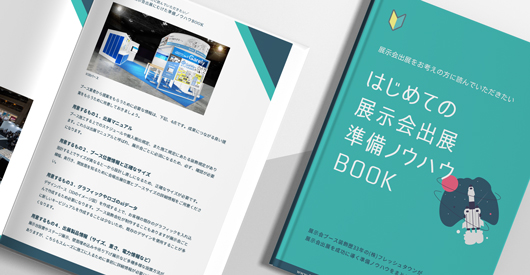展示会後のフォローを成功させる方法とは?|フォローから商談獲得
INDEX

展示会においてリードを多く獲得できたとしても、その後のフォローが適切でなければ商談にはつながりません。展示会で得られる名刺や来場者リストは、単なる接点ではなく、将来の顧客を生む貴重な情報源です。だからこそ、展示会後のアフター活動は、マーケティング活動の中でも非常に重要な位置づけとなります。
本記事では、フォローアップを効果的に行うための準備から、メールや電話を使ったアプローチ、リード管理の仕組み、そして商談獲得へとつなげる実践的な方法を紹介します。展示会の成果を最大化するために、見込み客との関係構築に必要なステップや手法を解説します。
展示会後の成果を左右するフォローアップの重要性
展示会は、自社の製品やサービスを直接紹介できる貴重なマーケティングの場であり、多くの見込み客と接点を持つことができます。しかし、展示会当日の対応だけで満足してしまい、フォローアップをおろそかにしてしまうと、せっかくの機会を無駄にしてしまう可能性があります。
展示会後のフォローは、リードの確度を見極め、興味や関心を持つ来場者に継続的なアプローチを行うための起点です。特に、名刺交換をしただけでは商談にはつながらず、その後の対応やアクションの質が問われます。リードのデータ化やCRMへの登録、リストの整理など、事後の準備が商談化の成功に大きく影響します。
また、展示会終了直後のタイミングでアプローチすることが、記憶が鮮明なうちに関係を深めるチャンスにもなります。特に、フォローアップメールや電話での連絡は、顧客情報をベースにした個別対応が重要であり、無差別な一斉送信ではなく、セグメントされたメッセージの送信が求められます。
なぜ展示会後の対応が営業成果を左右するのか?
展示会で得たリードは、まだ「興味段階」にある場合が多く、放置してしまうと関心が薄れ、競合他社へと流れてしまうリスクがあります。特に、アプローチまでに時間が空いてしまうと、見込み客の意欲は急速に低下していきます。
だからこそ、展示会終了後の翌日には、お礼や資料送付などの初期対応を迅速に実施する必要があります。これにより、相手の記憶に自社の印象を残し、商談へと進むための第一歩を踏み出すことができます。
営業担当者が適切なシナリオとタイミングで対応を行うことで、リード育成を効率的に進めることができ、結果的に成果につながる確率が高まります。展示会の本当の価値は、開催当日ではなく、その後の対応にあるといっても過言ではありません。
事前準備で差がつくフォロー活動のステップ
展示会でのフォローアップを成功させるには、事後の対応だけでなく、事前の準備が鍵を握ります。ブースでの対応や資料配布も重要ですが、それ以上に重要なのが、会期後のフォロー施策をあらかじめ設計しておくことです。営業チームやマーケティング部門が連携し、リード獲得後の流れを明確にしておくことで、成果を最大化できます。
まず、来場者の情報収集を行うためのアンケートやヒアリングシートを用意し、会話内容や興味関心の有無を記録できるようにしておくことが大切です。これにより、展示会後に実施するフォローが属人的にならず、組織的なアプローチにつながります。
次に、対応フローのステップを事前に決めておくことも重要です。たとえば、「初回メール→3日後に架電→1週間後にDM送付→10日後に再架電」など、接触のタイミングを明文化し、CRMなどのツールで管理する体制を整えましょう。
展示会前にやっておくべき準備とシナリオ作成
展示会前にフォローのシナリオを構築しておくことで、会期後の対応がスムーズになります。シナリオとは、見込み客がどのようなフェーズにあるかを想定し、それぞれに適したアプローチ内容とツール、担当者を明確にする設計図のようなものです。
例えば、「情報収集目的の来場者」「検討段階にある来場者」「すぐにでも導入したい企業」など、セグメントごとに対応策を変える必要があります。そのためには、リード情報のデータ化やヒアリング内容の整理を迅速に行い、担当を明確に割り当てる体制が不可欠です。
また、配信するメールの文面や件名も事前に複数パターンを作成しておくことで、開封率の向上や効果的なアプローチが可能となります。マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用すれば、自動での配信や開封のトラッキングも行えるため、効率的なフォロー活動が実現します。
メールと電話を活用した効果的なアプローチ方法
展示会後のフォローアップで最も基本的かつ重要な手法が、メールと電話によるアプローチです。中でも、初動となるお礼メールは、展示会での接点を自然につなげる重要なコミュニケーションとなります。来場者が展示会の内容をまだ覚えているうちに、できれば翌日には送信を行うのが理想です。
メールのポイントは、文面が一方的でないことです。資料の添付やWebページへのURLを案内するだけでなく、「何に関心を持ったか」「どのような課題があるか」といった部分に触れ、相手に寄り添った内容にする必要があります。また、メールの件名は開封率を左右するため、「展示会ご来場ありがとうございました」などのシンプルかつ具体的な表現が効果的です。
加えて、電話でのフォローも忘れてはなりません。名刺交換だけで終わったリードに対して、状況やニーズを確認するヒアリングを行うことで、商談の可能性を見極めることができます。受付時間や都合を考慮したタイミングで架電することが重要です。
顧客の興味を引き出すフォローアップメールの例文とコツ
メール文面を作る際のコツは、「感謝」、「目的」、「行動喚起」の3点を明確に伝えることです。以下に基本的な例文を示します。
件名例:【展示会】ご来場のお礼と資料送付のご案内
本文例:
〇〇様
先日は弊社ブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
当日ご案内させていただきました□□製品の資料を添付いたしますので、ぜひご確認ください。
ご不明点やご質問等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
このように、文面には「誰に向けた内容なのか」、「どの製品やサービスに触れたのか」、「次にどうしてほしいのか」が含まれていることが大切です。また、MAツールを導入している場合は、クリックや開封のデータを元に、セグメントごとに内容を変えることも有効です。
メルマガ形式での一斉送信よりも、個別に最適化された情報を提供する方が、受注やアポイントにつながる確率は高まります。
名刺・リード情報の整理とCRMへの反映手法
展示会後に収集した名刺やアンケートなどの情報は、適切にデータ化し、すぐにCRMやリード管理ツールへ取り込む必要があります。これが遅れると、見込み客との関係構築や次のアプローチの質に大きな影響を及ぼします。まず重要なのは、収集データを整理し、部署や業種、関心領域などのセグメントに分類することです。
情報を正確に整理することで、メールやDMの配信対象を明確にでき、無駄な労力やコストの削減にもつながります。また、リスト化した情報は、マーケティングオートメーションツールで一斉送信や個別対応のシナリオ作成にも活用可能です。
CRMへの登録時には、来場日や会話内容、関心を示した製品などの情報もセットで入力し、次回接触時の参考とするべきです。これにより、継続的な育成活動がスムーズに進みます。
見込み顧客への最適なアプローチ方法とは?
見込み顧客は段階によって必要な対応が異なります。まだ情報収集中のリードには、メルマガなどでの情報提供が適しており、すぐに導入を検討している企業には、アポイントや訪問などの直接対応が求められます。
そのためには、事前に用意したヒアリングシートやシナリオをもとに、それぞれのリードがどのフェーズにあるかを把握しておく必要があります。さらに、データの更新を定期的に行い、常に最新の状況に基づいた判断ができるようにしておくことも重要です。
また、アプローチの際には、相手の立場や業種、関心のある製品に合わせた提案を行うことで、反応率を高めることができます。ここでもCRMやMAツールを活用すれば、効率的かつ戦略的な対応が可能になります。
商談獲得につなげるためのフォローアップ戦略
展示会後のフォロー活動の目的は、単なる関係構築にとどまらず、最終的には商談獲得へと結びつけることです。そのためには、リードの確度や意欲に応じた柔軟なアプローチが不可欠です。見込み客を中長期的に育成しながら、タイミングを逃さずアポや提案へとつなげるための仕組みが必要です。
まず重要なのは、すべてのリードに対して同じ対応をするのではなく、段階ごとにセグメントし、それぞれに合った施策を展開することです。たとえば、「情報収集中」「検討中」「導入直前」といったフェーズに分類し、それぞれに異なるフォロー内容や接触頻度を設計します。
また、MAツールを活用したスコアリングで、行動データ(例:メール開封、URLクリック、資料請求など)を分析すれば、より効果的なタイミングでアプローチが可能となります。全員に手動で対応するのではなく、自動化を上手に取り入れることが、効率的なフォロー活動につながります。
よくある失敗と成功に導くポイント
フォローアップでよくある失敗の一つは、「展示会の記憶が薄れる前に連絡しよう」と思いながら、実際の連絡が数日遅れてしまうケースです。タイミングを逃すと、せっかくの印象も薄れ、他社にリードを奪われる可能性が高まります。これを防ぐためには、会期終了から翌日までに初回の接触を完了させるようなルールをチーム内で共有しておくことが重要です。
また、「とりあえず資料を送る」だけのフォローでは、相手にとっての価値が伝わらず、反応を得られません。相手のニーズや課題に即した情報提供を意識し、場合によっては個別の課題に対する提案型のアプローチを行う必要があります。
一方、成功につながるポイントは、「継続的な接触」と「段階に応じた対応」です。展示会直後だけでなく、定期的にメルマガや無料セミナーの案内などを通じて関係を維持することが、長期的な信頼構築と受注につながります。
まとめ:展示会出展後のフォロー活動
展示会の成果を最大限に活かすには、当日のリード獲得だけでなく、その後の継続的なアフター営業が必要不可欠です。展示会後のフォローは、顧客との最初の接点から受注、さらには中長期的な関係構築へと発展させる仕組みを持つことが成功の鍵となります。
☞展示会出展の効果を最大化するためのフォロー活動
1. 迅速な初回連絡の実施
・ 展示会終了直後、できれば翌日中にお礼メールや資料送付を行い、記憶が鮮明なうちに接点を維持する。
2. 事前準備とシナリオの構築
・ 展示会前にヒアリングシートやアンケートを用意し、各リードに応じたフォローアップの流れ(例:初回メール→3日後の架電→1週間後のDM送付)を策定しておく。
3. メールと電話による個別アプローチ
・ 資料添付や具体的な提案を含む、感謝・目的・行動喚起が明確なメール送信と、ニーズ確認のための電話フォローを実施する。
4. リード情報の整理とCRM登録
・ 収集した名刺やアンケートの情報を即時にデジタル化し、CRMなどのツールで一元管理して、適切なセグメント分けを行う。
5. 見込み客のセグメント化と対応の最適化
・ 見込み客を「情報収集中」「検討中」「導入直前」などのフェーズに分類し、それぞれに最適なフォローアップ内容と接触頻度を設定する。
6. マーケティングオートメーションの活用
・ MAツールを活用して、メール配信の自動化や開封率のトラッキングを行い、効率的かつ戦略的なアプローチを実現する。
7. 継続的な接触の維持
・ 展示会直後だけでなく、定期的なメルマガや無料セミナー案内などを通じて、長期的な関係構築と商談獲得につなげる。
8. 個別最適化されたパーソナライズドメッセージ
・ リードの関心や課題に合わせた内容で、無差別な一斉送信ではなく、個別対応を徹底する。
まずは、事前に用意した計画に沿って、資料送付やお礼メール、架電などの初期対応を素早く実施することが基本です。その上で、CRMやマーケティングオートメーションツールを活用し、段階ごとに適した施策を展開していくことが求められます。これにより、リードの育成や確度の判定がより精緻に行えるようになります。
また、社内でのルール整備やナレッジの蓄積も重要です。担当者任せにするのではなく、チーム全体でフォローアップのフローを共有し、PDCAを回すことで、継続的な改善が可能となります。成功事例や失敗事例の情報共有も、次回以降の展示会出展時の施策に役立ちます。
今後は、単なる一方通行の案内ではなく、顧客の状況や行動に応じた個別最適化されたコミュニケーションが求められます。SNSやWeb施策と連携したプロモーションも視野に入れ、効率的かつ戦略的なマーケティングを展開していくことが重要です。
お役立ち資料
CASE STUDY
創業以来培ったノウハウとデータをもとにまとめたハンドブックです。
「初めての展示会で何をやったら良いかわからない」「効率的に成果を出すブースづくりについて知りたい」、そんな方におすすめです。
本資料は展示会出展社さま、展示会出展をご検討されている方に向けて作成した資料です。 同業他社さまには資料ダウンロードをご遠慮いただいております。申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。