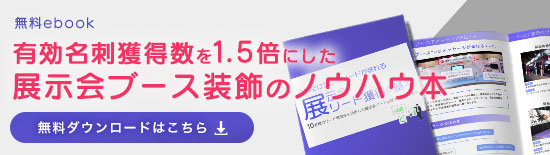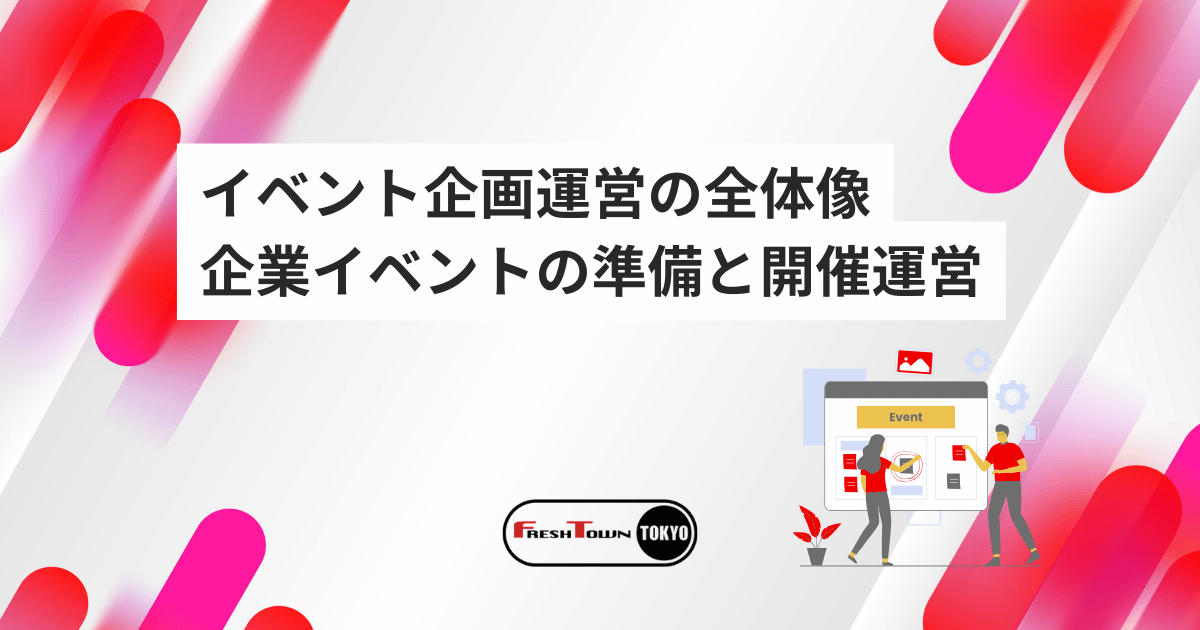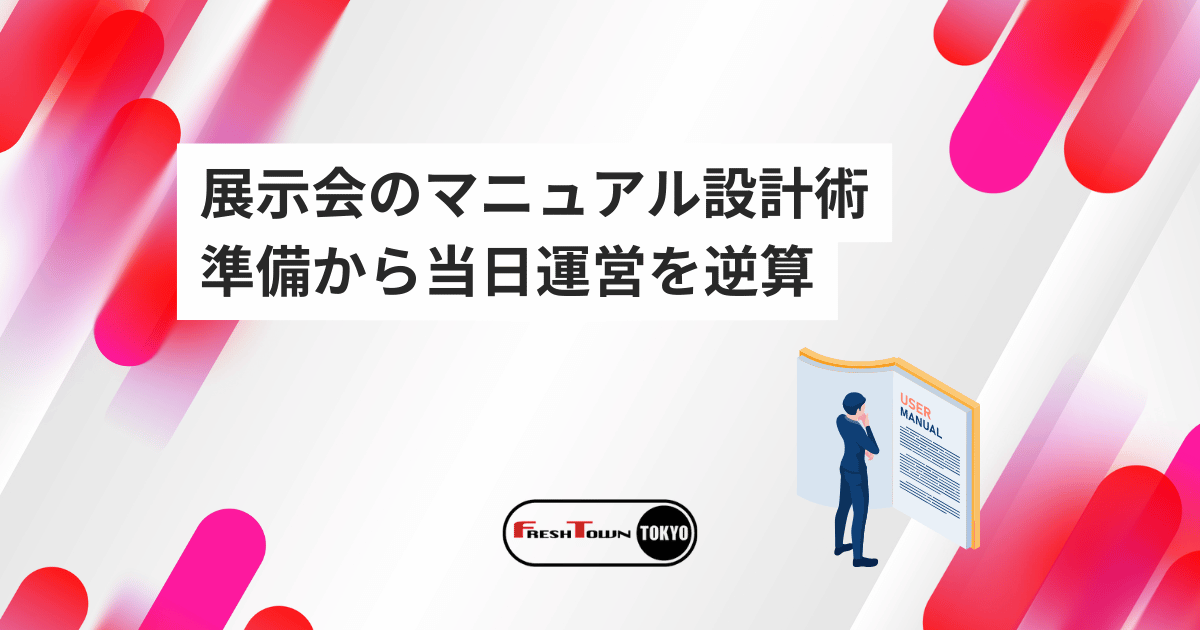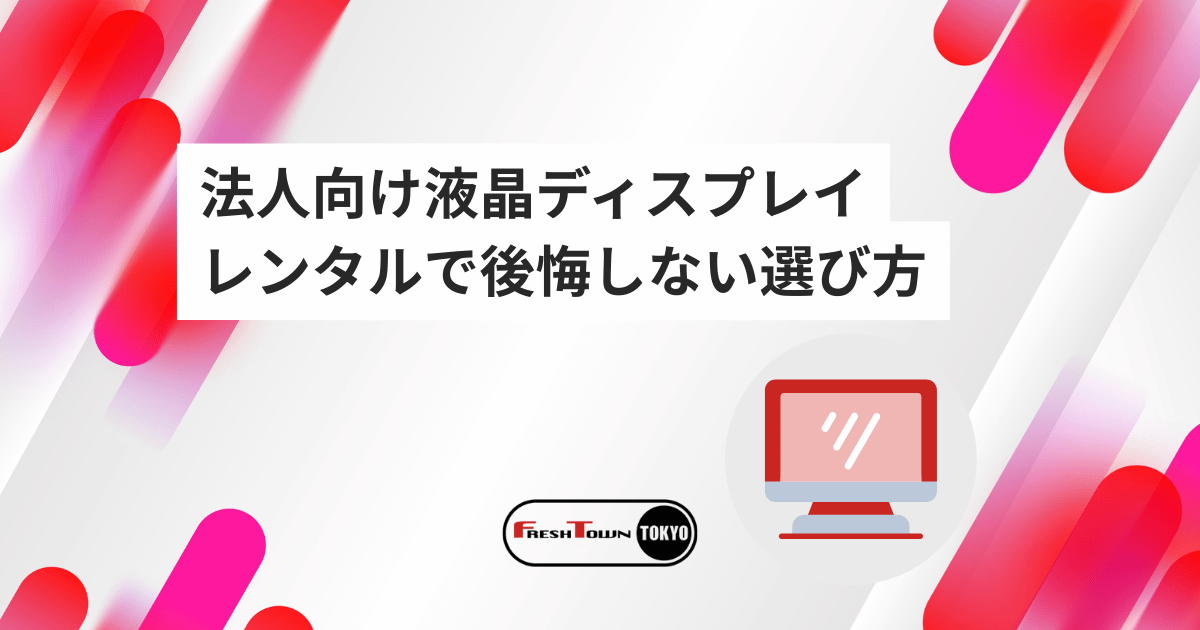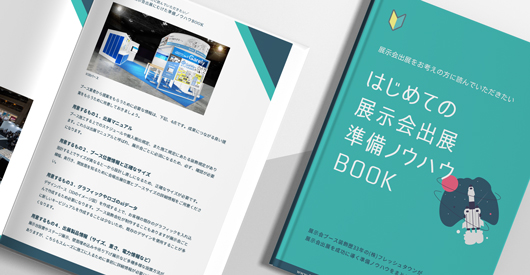展示会成功のカギは説明員|事前準備から当日まで徹底解説
INDEX

展示会の成果は、ただ魅力的なブースを用意するだけでは得られません。最前線で来場者とコミュニケーションを取る「説明員」の準備と行動こそが、成功のカギを握ります。彼らの接客力やトーク内容、名刺交換の対応ひとつで、得られるリードの質も数も大きく変わるのです。
本記事では、展示会における説明員の「役割」「事前準備」「当日の行動」「フォローアップ」に至るまでを順を追って解説します。さらに、企業としてのマーケティング視点を取り入れた行動計画の立て方や、成果につながる営業プロセスの具体例も紹介します。
「展示会での集客や成果が思うようにいかない」「説明員の派遣だけで終わっている」と感じている担当者の方は、ぜひこの記事を参考にして、次のイベントでの成果向上を目指してください。
展示会における説明員の重要性と役割
展示会においては、どれだけ優れた商材やブース装飾を用意しても、最終的に来場者の印象を左右するのは現場に立つ「説明員」です。彼らは単なる案内係ではなく、企業と顧客をつなぐ最初の接点であり、自社の魅力を伝える営業パーソンとしての側面も持ちます。
説明員の役割には以下のようなものがあります。
・ 来場者の関心を引くための声かけと受付対応
・ ニーズを把握しながら、適切な情報を提供するためのトーク
・ 名刺交換や資料の配布によるリード獲得
・ 製品やサービスに対する質問への対応
・ 競合他社との差別化ポイントの明確なアピール
このように、説明員は単なる「話し手」ではなく、「成果を左右する要因」として機能します。特に商談の入り口となる場面では、話し方ひとつ、態度ひとつが印象を大きく左右し、リードの質に直結します。
また、展示会は短期間で多くの情報が飛び交う特殊なイベントです。そのため、現場のスタッフには、瞬時に相手の関心度を見極める「アジリティー」が求められます。適切な対応ができる説明員が揃えば、それだけで展示会全体の成果は大きく変わるのです。
なぜ説明員の存在が集客・成果に直結するのか
展示会は多くの企業が出展し、参加者が一度に多くの情報を受け取る場です。そのため、いかにして興味を持ってもらえるかが鍵となります。説明員は、展示されている製品やサービスの価値を「対面」で伝える唯一の手段であり、来場者がブースに立ち止まるかどうかを決める重要な要素です。
成功している企業に共通するのは、以下のような説明員の特徴です。
・ 基本マナーやマニュアルに則った丁寧な対応
・ 短時間で相手の課題を引き出す質問力
・ スクリプトに頼らず、柔軟なトーク
・ ノベルティや資料を効果的に活用
・ 来場者ごとに適したアプローチ
このような説明員がいると、来場者の関心度合いも高まり、名刺交換率や見込み顧客の獲得数も向上します。逆に、準備不足の説明員では、せっかくの展示会も失敗に終わる可能性があります。
展示会準備段階での行動計画と心構え
展示会の成功には、「当日どう動くか」よりも、「事前に何を準備するか」が圧倒的に重要です。特に説明員にとっては、明確な行動計画と、それを支える心構えが成果を大きく左右します。
まず、出展目的を明確にした上で、以下の点を軸に準備を進めることが求められます。
・ 参加者の流れを想定したブース配置と導線設計
・ トークスクリプトやパンフレットなどの資料準備
・ 担当者ごとの役割分担とロープレによる動きの確認
・ 想定質問と回答集のマニュアル化
・ セミナー開催の有無、時間帯別の担当割り当て
・ ノベルティや配布物の最終確認
また、展示会では想定外のトラブルも起こりがちです。そのため、搬入から装飾設置、受付対応まで、タイムスケジュールに余裕を持たせることも大切です。
事前準備を入念に行っておくことで、当日の行動にアジリティーが生まれ、来場者一人ひとりへの適切な対応が可能になります。
行動計画の立て方とNGな準備例
効果的な行動計画を立てるには、まず目標を明確に設定し、その達成のために必要な要素を逆算することが基本です。たとえば、以下のような目標が想定されます。
・ 名刺交換数の目標(例:100枚/日)
・ 見込み顧客の獲得数(例:20件以上)
・ 自社製品への関心が高い来場者の割合(例:50%以上)
それに対して、ありがちなNG行動も把握しておく必要があります。
・ トークの練習不足 → スムーズな提案ができず機会損失
・ 担当者の役割不明確 → 同じ対応を複数人が実施し混乱
・ 資料や備品の直前準備 → 搬入や設営に遅れ
・ ノルマ未設定 → 成果が曖昧になり、効果測定不可
さらに、教育が不十分なまま派遣されたスタッフが、来場者に不信感を与えるケースも少なくありません。説明員全員が展示会の目的や商材の内容をしっかり理解していることは、最低限の準備として押さえておきたいポイントです。
ターゲット設定と訴求ポイントの明確化
展示会で成果を上げるには、やみくもに多くの来場者に声をかけるのではなく、「誰に、何を、どう伝えるか」を明確にしたターゲット設定と訴求ポイントの整理が不可欠です。
これはマーケティング戦略の基本であり、展示会でも例外ではありません。
まず、以下の観点からターゲットを明確化します。
・ 想定される業界や企業規模
・ 解決したい課題やニーズ
・ 商談につながる意思決定者かどうか
次に、自社のどの製品やサービスを軸にアピールするかを決め、来場者の目に留まるようにブースの装飾やキャッチコピーにも反映させます。
さらに重要なのが、説明員全員がその方向性を共有し、トークや対応に一貫性を持たせることです。伝えるべきポイントがバラバラでは、相手に届くものも届きません。
事前に以下のような共有を行うと効果的です。
・ ターゲット別のアプローチシナリオ
・ 強みを伝えるための比較資料や実績紹介
・ 商談化を意識した会話の展開方法
こうした下準備が、展示会当日のアプローチ精度を高め、限られた時間内での成果最大化につながります。
自社の強みと来場者のニーズをつなぐ方法
自社の強みを活かし、来場者の関心やニーズと結びつけるには、単なる機能説明では不十分です。以下のようなポイントに基づいた構成が重要です。
・ 【相手視点での課題提示】 「~でお困りではありませんか?」などの問いかけで、共感を得る
・ 【導入効果のイメージ共有】 他社事例や改善効果を具体的に伝える
・ 【視覚で訴える工夫】 ビジュアル資料や実機展示、タッチ&トライの体験型ブース
・ 【一言で伝える強み】 「最短3日で導入可能」「コストを30%削減」などのキャッチが効果的
また、説明員がニーズをうまく引き出すには、ヒアリング力も不可欠です。来場者の課題を「聞き出し、整理し、結びつける」一連のコミュニケーションこそが、展示会における成功の秘訣と言えるでしょう。
当日の接客対応で意識すべきポイント
展示会当日、スタッフ一人ひとりの行動が成果に直結します。特に接客の品質が低いと、どれだけ優れた商材や資料を用意していてもリード獲得にはつながりません。展示会では短時間のコミュニケーションが勝負。瞬時に信頼を得て、次につながる名刺交換や商談への導線をつくることが求められます。
当日の対応で意識すべき主なポイントは以下の通りです。
・ 第一印象の重要性: 清潔感のある服装と明るい挨拶で、信頼感を与える
・ 臨機応変な声かけ: 来場者の立ち止まり方や視線の動きに応じたアプローチ
・ 話しすぎない: 一方的に話すのではなく、相手の話を引き出すスタンス
・ 対応のメリハリ: 濃いリードには時間を割き、軽い興味層は資料で簡潔に案内
・ 役割分担の徹底: 説明、案内、フォローと、各自の動きが被らないよう整理
また、担当者全員が1日のスケジュールや目標(例:名刺○○枚獲得)を理解していることも、当日の行動を一貫させる上で重要です。教育や練習が不足していると、その場対応に時間を取られ、機会損失につながる恐れがあります。
名刺交換・トーク・資料配布のコツと注意点
接客の中でも特に成果に直結しやすいのが、「名刺交換→トーク→資料配布」の流れです。これらを効果的に行うには、ちょっとしたコツとマナーが成果を分けます。
名刺交換のコツ
・ 名刺はすぐ取り出せるようにしておく
・ 相手より低い位置で両手で渡すのが基本
・ 交換後、会社名や名前を会話で繰り返し、覚えようとする姿勢を見せる
トークの注意点
・ 導入トークは30秒以内を目安に、簡潔に価値を伝える
・ 興味があれば深掘り、なければ簡潔な案内で次に回す判断力が重要
・ 自社の「強み」を短く言語化しておくと有効
資料配布の工夫
・ 渡すだけでなく、ポイントを簡単に説明して渡す
・ パンフレットやノベルティとセットで印象に残す
・ 相手の興味度合いに応じて配布物の内容を変えると効果的
また、NG行動としては、集団で固まって雑談している、相手を選んで声かけをしている、話し方がマニュアル通りすぎるといったことが挙げられます。こうした行動は展示会全体の印象を損ねるだけでなく、リードの取りこぼしにもつながるため注意が必要です。
説明員教育とチームでの情報共有
展示会の成功には、現場で働く説明員のスキルと、チームとしての情報共有体制が大きく影響します。個人の努力だけでは限界があり、全体として統一された対応ができてこそ、来場者の満足度や信頼感を高めることができます。
事前の教育では、以下のような項目を中心に進めると効果的です。
・ 製品・サービスの特徴や導入事例の理解
・ トークスクリプトの読み合わせとロープレ
・ 名刺交換や立ち居振る舞いのマナー確認
・ 想定される質問と回答の整理
・ 来場者の関心度に応じた対応方法の訓練
また、担当者全員が展示会の目的と目標(例:名刺〇枚獲得、〇件の商談化)を正しく理解していないと、対応にバラつきが出て成果が分散してしまいます。
チーム内の情報共有においては、以下のような施策が有効です。
・ 朝礼や昼礼での情報交換タイム
・ 見込みリードの共有と評価
・ フィードバックの即時共有による改善のサイクル
・ 終了後のミーティングで得られた課題の整理
スタッフ同士の連携が取れていれば、混雑時の対応分担もスムーズになり、より多くの来場者に対応できる可能性が高まります。これはアジリティーの向上にもつながり、展示会の現場で非常に重要な要素です。
トークスクリプトや想定Q&Aの活用方法
事前に用意する「トークスクリプト」と「想定Q&A集」は、説明員の質を底上げするために非常に有効なツールです。ただし、あくまで“ガイドライン”として活用し、機械的に話すのではなく、自然な会話の中で活かすことが重要です。
トークスクリプトのポイント
・ ターゲット別に複数パターン用意する
・ 展示物に応じて製品・サービスごとに分ける
・ 「30秒・1分・3分」など会話の尺で分類する
想定Q&Aの活用方法
・ 実際に過去の展示会であった質問をベースに作成
・ 回答は短く明確に。数値や実績を盛り込むと効果的
・ チーム内での共有と更新をルール化する
このような準備があることで、説明員は安心感を持って対応に臨むことができ、結果として成果につながります。また、未経験の社員でもある程度の質を保った応対が可能になるため、社内リソースの有効活用にもなります。
展示会後のフォローアップと成果最大化
展示会の成功は、当日で終わるものではありません。むしろ、終了後のフォローアップこそが、商談の有無や受注の確度を左右する重要なフェーズです。展示会はあくまで接点獲得の場に過ぎず、本当の意味での「成果」は、その後のアプローチによって形になります。
まず重要なのは、イベント終了後すぐに名刺や資料を整理し、リードの分類を行うことです。対応のスピード=アジリティーが、そのまま相手への印象となって返ってきます。
以下のようなアクションが効果的です。
・ 名刺情報を即日CRMや管理シートへ入力
・ 興味度合い別に「A(即アプローチ)/B(様子見)/C(情報提供)」で分類
・ 見込み顧客には2~3営業日以内にフォローメールや電話を送付
・ 商談に進みそうな相手には、個別提案や訪問の打診を行う
・ 課題や要望が明確だった来場者には、事例資料や改善提案を送る
また、イベント中に拾いきれなかった反応も、整理を通して見えてくることがあります。担当者ごとに「誰がどの相手に対応したか」を記録しておくことで、フォローの質も向上します。
展示会後のフォロー方法について詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会後のフォローを成功させる方法とは?|フォローから商談獲得
も是非ご一読ください。
担当者によるアフターフォローとアジリティーの活かし方
展示会の担当者は、準備〜当日運営〜終了後の営業活動までを一貫してリードすることが理想です。その中で重要になるのが、「アジリティー(素早い対応能力)」と「行動量」です。
特に展示会後のフォローでは、以下のようなアジリティーが成果を左右します。
・ 名刺交換した相手には即日お礼メールを送信
・ 要望があった資料や事例を、翌日には送付
・ 話が盛り上がった相手には、フォロー訪問の予定を早期に調整
・ 展示会の反応をチームで早めに共有し、次回の改善点を抽出
こうした動きは、企業全体の対応品質を高め、相手に対して「信頼できる会社だ」という印象を与えます。逆に、フォローが遅れたり、やり取りが属人的になると、せっかくの展示会が無駄になる可能性もあります。
このように、展示会後も継続的な提案活動を行うことで、単なる「名刺収集イベント」ではなく、本当の意味での営業成果につながるのです。
展示会後のアフターフォローについて詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会後のフォローを成功させる方法とは?|フォローから商談獲得も是非ご一読ください。
まとめ:展示会で成果を出す説明員の行動とは
展示会の成功には、説明員の役割が決定的です。準備不足や現場対応の甘さは、せっかくの出展を無駄にしかねません。逆に言えば、現場の説明員が「誰に、何を、どう伝えるか」を明確にし、確実な対応を実践すれば、それだけでリード獲得や商談化の可能性は飛躍的に高まります。
展示会成果を最大化するための要点を以下にまとめます。
☞展示会の成果を左右するのは、説明員の準備と行動力
1. 目的と目標の明確化
「名刺〇枚獲得」「商談〇件創出」など、具体的なKPIを事前に設定
2. 行動計画と教育の徹底
トークスクリプトやQ&Aの準備、ロールプレイの実施で現場対応力を養成
3. ブース設計と役割分担の最適化
導線・配置・装飾を工夫し、説明員に明確な役割を与える
4. 接客対応の基本を重視
第一印象、名刺交換、トーク展開のマナーと技術を共有
5. 来場者の興味とニーズの把握
自社の強みを相手の関心と結びつけて訴求力を強化
6. 展示会後の迅速なフォローアップ
リードの即時整理、分類、アプローチで営業成果に直結
7. チーム全体での情報共有と改善サイクル
会期中の課題と成功事例を蓄積し、次回に活かす体制づくりを意識
これらを実行することで、「行き当たりばったりの出展」から「営業成果に直結する展示会」へと進化させることが可能になります。企業としてのマーケティング活動の一環として展示会を戦略的に捉え、ぜひ説明員の力を最大限に活かしてください。
お役立ち資料
CASE STUDY
創業以来培ったノウハウとデータをもとにまとめたハンドブックです。
「初めての展示会で何をやったら良いかわからない」「効率的に成果を出すブースづくりについて知りたい」、そんな方におすすめです。
本資料は展示会出展社さま、展示会出展をご検討されている方に向けて作成した資料です。 同業他社さまには資料ダウンロードをご遠慮いただいております。申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。