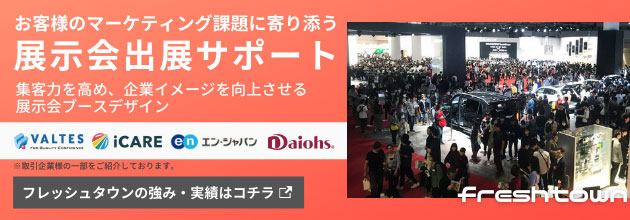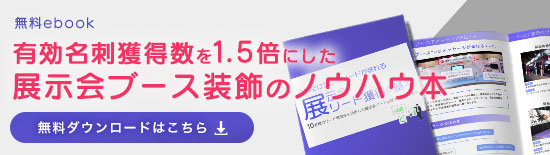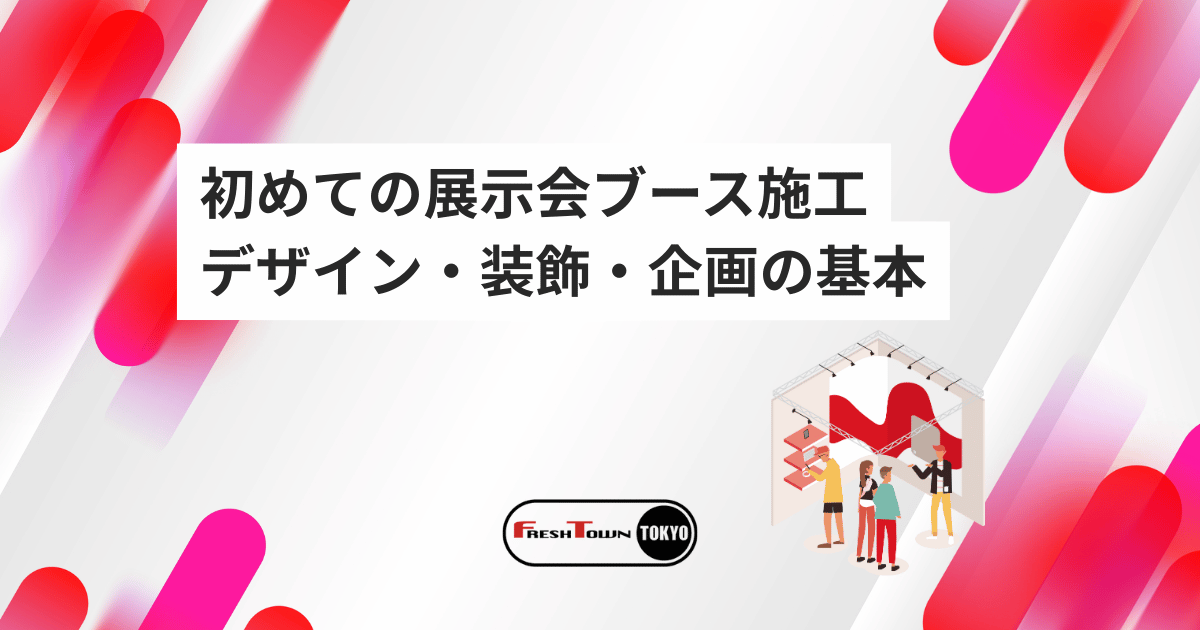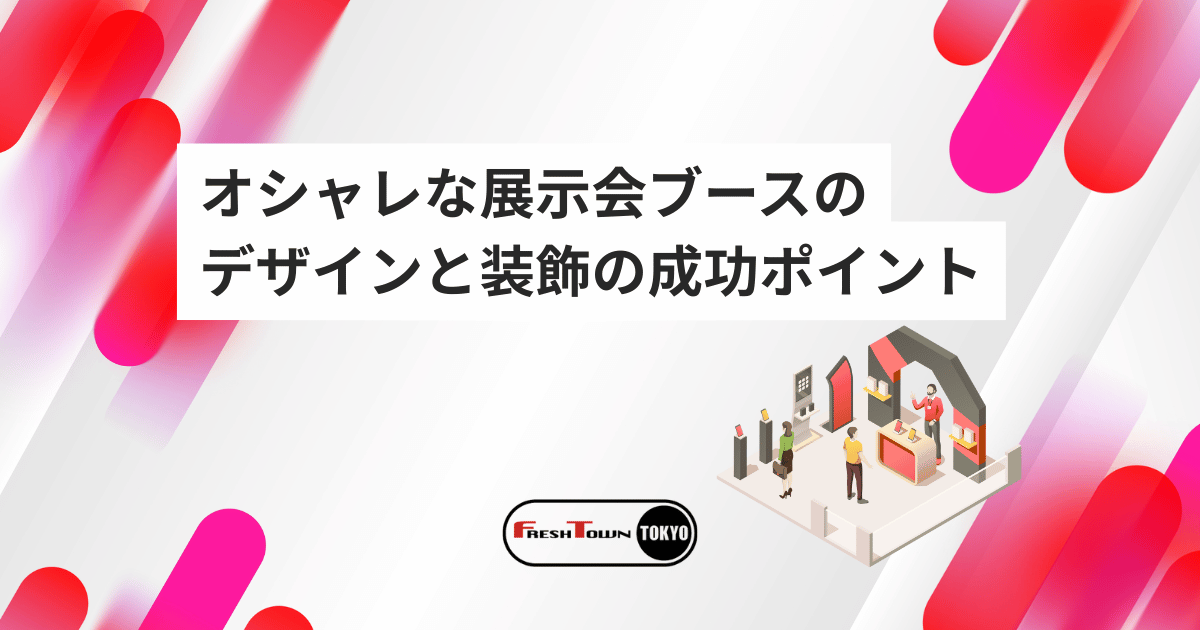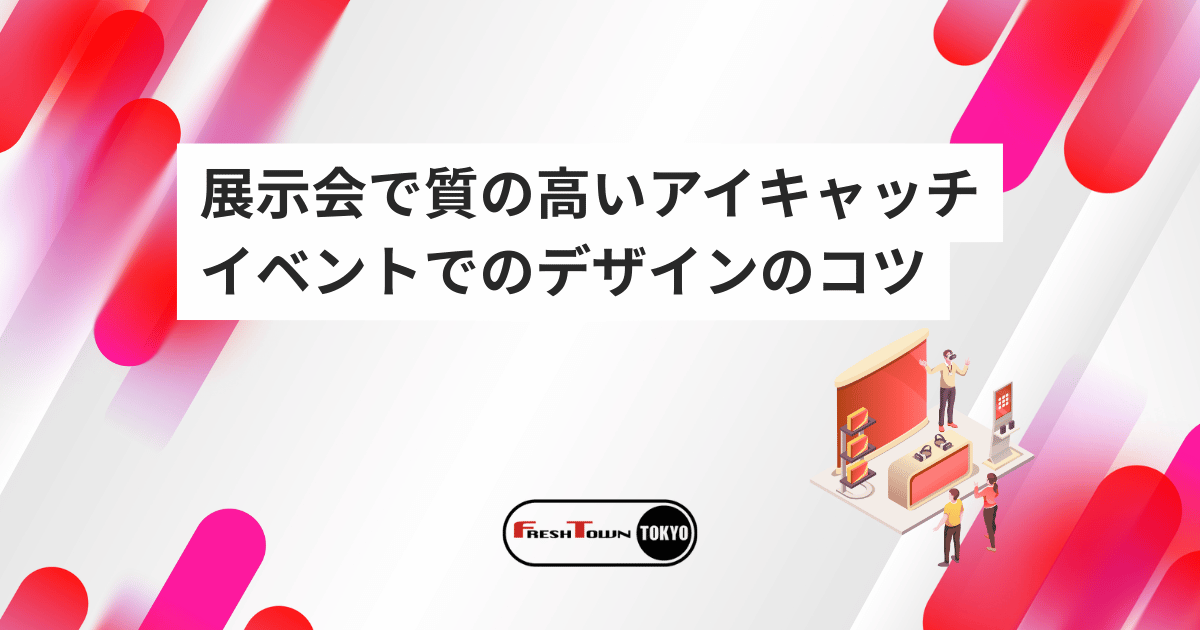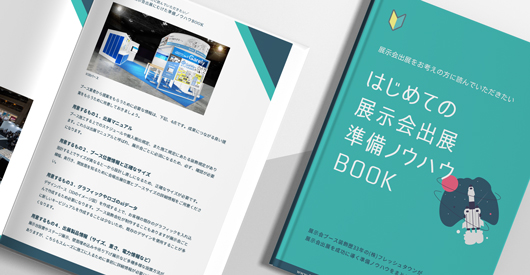展示会パネルの印刷・掲示で差をつける5つの工夫
INDEX

展示会におけるパネル掲示は、限られた空間と時間の中で来場者の注意を引き、訴求力のあるメッセージを届けるための重要な手段です。印象的なデザイン、適切なサイズ選び、効果的なスタンドやボードの使用など、成功する展示にはいくつもの工夫が必要です。
本記事では、展示会パネルの制作から掲示方法、さらには来場者の動線や視線を意識したディスプレイまで、差がつくポイントをわかりやすく解説します。展示会に初めて参加する企業だけでなく、すでに出展経験のある方にも役立つ、実践的なノウハウが満載です。
来場者に選ばれる展示を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
展示会パネルの基本と目的を知る
展示会におけるパネルは、企業のブランドや製品、サービスを的確に伝えるための「顔」とも言える存在です。多くの来場者が限られた時間の中で多くのブースを回る中、展示会パネルの第一印象がその企業の記憶に残るかを大きく左右します。
基本的にパネルは、用途や設置場所に応じてサイズや材質を選択し、伝えるべき情報を整理したうえで構成・作成されます。展示会の目的や来場者のペルソナを明確にしたうえで、内容の優先順位を決定し、視覚的に訴求力のある表現を用いることが大切です。
さらに、使用する素材にはスチレンボードやアルミフレームパネルなどがあり、屋内・屋外での使用や設置期間によって適切なものを選ぶ必要があります。パネルのタイプごとの違いを把握し、設営や撤収のしやすさも加味した設計が求められます。
来場者が思わず足を止めたくなるようなパネルを実現するためには、単に目立つだけでなく、ブランドの世界観やメッセージを明確に伝えることが重要です。
展示の効果を最大化するための考え方
効果的な展示を実現するためには、単なる見た目の派手さに頼らず、目的とペルソナに基づいた戦略的なパネル制作が不可欠です。以下のポイントが成功のカギとなります。
・ ターゲットの明確化
誰に向けた展示なのかを明確にし、関心を引く要素(色、フォント、キャッチコピーなど)を
盛り込むことが大切です。
・ ストーリー性のある配置
単に情報を羅列するのではなく、導入→問題提起→解決策→訴求という流れを意識した構成
が効果的です。
・ 視線誘導の工夫
文字の大きさや配置、背景色などを使い分けることで、自然に視線を導くことが可能です。
・ パネル以外のアイテムとの連動
バナー、卓上ポスター、ディスプレイ装飾と一貫したデザインで統一感を出すと、ブース全体の
印象が格段に向上します。
このように、展示会におけるパネルは単なる情報掲示物ではなく、企業の魅力を最大限に引き出すツールとして活用すべきです。パネル設計に戦略を組み込むことが、来場者との有意義な接点の第一歩となります。
パネルデザインのステップと作り方
展示会において注目を集めるためには、パネルのデザインに工夫が必要です。ただ見やすいだけでなく、企業のイメージや製品の特性を的確に伝えることが求められます。ここでは、効果的なデザインに至るまでのステップを解説します。
デザイン作成の基本ステップ
1. 目的の明確化
展示会における自社の目的(認知拡大、販促、商談など)を定め、それに合わせたパネル内容
を設計します。
2. 構成の設計
ターゲットとなる来場者の目線に立って、どのような情報が必要か、どの順序で提示すべきか
を整理します。
3. 入稿データの作成
印刷会社の指定する仕様・サイズに従い、解像度や色モードなどの基準に適合したデータを
作成します。Ai形式での入稿が一般的です。
4. 校正と修正の確認
誤字脱字やレイアウトのズレなどがないよう、校正を丁寧に行いましょう。
5. 印刷と出荷スケジュールの確認
納期や出荷日、営業日の確認を事前に行い、設営日までに余裕を持って対応できるように
しておきます。
このように、単に見た目の良さを追求するのではなく、情報設計から入稿までの流れを把握しておくことが重要です。
訴求力を高めるデザインの工夫と注意点
パネルデザインには「目立つだけ」でなく、「伝わること」が求められます。そのためには以下のような工夫が効果的です。
デザインで意識すべき要素
・ キャッチコピーの配置とフォント選び
印象に残る短いメッセージを視線の集まりやすい位置に配置し、読みやすいフォントを選ぶ
ことが大切です。
・ カラーと配色のバランス
企業のブランドカラーを軸にしながら、目立ちすぎず、視認性を保つカラー配色を心がけます。
・ 画像とイラストの活用
文字情報だけでは伝わらない視覚的な理解を助ける画像や図解を積極的に使用しましょう。
・ 空白(ホワイトスペース)の効果
情報を詰め込みすぎると見づらくなります。読み手の視線を休ませるスペースも必要です。
注意点
・ 文字量が多すぎないかチェック
短時間で情報を理解してもらうために、キーワードを強調しながらも簡潔な表現を心がけ
ましょう。
・ サイズに合わせた可読性の確保
遠くからでも視認できるよう、重要な情報は大きく、補足は小さくというメリハリをつけ
ます。
・ 印刷段階での色の再現性
モニターと印刷で色が異なることがあるため、色校正の依頼や実物サンプルでのチェックも
有効です。
これらの工夫により、展示会パネルの訴求力が格段に向上し、ターゲットにしっかりと届くデザインが実現します。
印刷と制作の流れを押さえる
展示会パネルの印刷と制作は、納期やコスト、仕上がりの品質に大きく関わる工程です。効果的な展示を実現するには、あらかじめ流れを把握し、スムーズに制作を進行する体制を整えておくことが重要です。
基本的な印刷・制作の流れは以下のとおりです。
1. 仕様の決定と見積り
展示スペースや内容に応じたサイズ、材質、数量を検討し、業者に見積もり依頼を行います。
ロットが大きいほど単価が安くなる傾向にあります。
2. データの作成・入稿
指定された形式(例:Ai、PDFなど)でデザインデータを作成し、マイページやメール、WEB
フォームから入稿を行います。
3. 校正・修正対応
入稿後、校正が入る場合は誤植や画像解像度の確認・修正を迅速に対応します。
4. 印刷工程の開始
校了後、正式に印刷がスタートします。印刷方式や加工オプション(例:ラミネート加工、
穴あけ)などにより制作時間や価格が変動します。
5. 出荷と納品
通常は数営業日以内に出荷されますが、急ぎの場合は当日出荷や短期対応が可能なプランを
選ぶと安心です。
制作をスムーズに進めるコツは、事前に仕様を明確にすることと、納期までの余裕を持ったスケジュールを組むことです。注文や問い合わせの際の注意点をまとめておくと、後々のトラブル防止にもなります。
用紙やスチレンボードなど素材の選択と比較
パネルの印刷に使用される素材の選択は、仕上がりの印象や耐久性、設置場所の制約に大きく影響します。用途に応じて最適な素材を選ぶためのポイントを以下に整理します。
主な素材とその特徴
・ スチレンボード(発泡ボード)
軽量で加工しやすく、屋内の短期イベント向けに最適。厚みやサイズ展開も豊富で、取り扱い
やすいのが特徴です。
・ 合成紙(ユポなど)
耐水性・耐久性があり、ややコストは高めですが高品質な表現が可能です。屋外や長期間使用
にも対応できます。
・ ファブリック素材(布地)
折りたたみや持ち運びが可能で、布バナーやタペストリーに使われます。シワになりにくく、
環境にも配慮された素材として人気です。
・ 光沢紙・マット紙
色鮮やかに仕上がる光沢紙は視覚的インパクトが強く、落ち着いたトーンを演出するなら
マット紙が有効です。
・ アルミ複合板や屋外用ボード
耐久性と重厚感を求める場合はこれらの素材がおすすめです。屋外展示や長期常設展示向け
として活用されています。
比較ポイント
| 素材 | 耐久性 | 重さ | 価格帯 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| スチレンボード | △ (短期) |
◎ (軽量) |
低価格 | 屋内イベント |
| 合成紙 | ○ (中期) |
○ | やや高め | 屋外展示も可 |
| ファブリック | △ (短期) |
◎ | 中価格 | モバイル展示 |
| 光沢紙 | △ | ◎ | 低価格 | ビジュアル 訴求重視 |
| アルミ複合板 | ◎ | △ (やや重) |
高価格 | 屋外・長期 展示 |
素材を選ぶ際は、掲示する期間・会場の環境・予算を加味しながら比較検討することが重要です。展示会の成功には素材の選択が土台になるとも言えるでしょう。
掲示とスタンドの使い分けテクニック
展示会におけるパネルの掲示方法は、単に貼るだけでなく、視認性や来場者導線、設営のしやすさまで考慮する必要があります。スタンド、パーテーション、壁面、卓上など、掲示の方法によって演出や効果が変わるため、それぞれの特徴を理解し、適切に使い分けることが重要です。
主な掲示方法の種類と特徴
・ スタンドタイプ
自立式で設置が簡単。背面パネルやのぼり旗との連動にも便利で、遠くからの視認性も高い
です。サイズ展開が多く、軽量タイプや屋外用の重厚型など選択肢も豊富です。
・ パーテーション掲示
ブースの間仕切りを活用してパネルを貼る方法。壁面全体を活かせるため、空間演出との相性
が良いです。テープ固定やマジックテープ、フックを使うなど、設営方法も自由度が高くなり
ます。
・ 壁面固定(両面テープ・フック使用)
展示会場の壁や背面ボードに直接固定する方法。余計な器具を使わず、すっきりとした印象に
仕上がりますが、壁面仕様や設営制限に注意が必要です。
・ 卓上設置
受付カウンターやテーブルの上などに小型パネルを設置するスタイル。商品説明、案内、販促
ツールとの連携に効果的です。
掲示方法を選ぶ際は、展示会場の設備規定・スペースの広さ・パネルのサイズや重量などを総合的に考慮することが求められます。
卓上パネル・パーテーション利用の具体例
限られたスペースで最大の訴求効果を出すためには、卓上やパーテーションを活用した掲示が非常に有効です。以下に、実際の展示でよく使われる事例を紹介します。
卓上パネル活用例
・ 製品の説明ツールとして設置
パンフレットやチラシと合わせて、製品の特徴やメリットを簡潔に紹介する内容を卓上パネル
にまとめておくと、来場者が手に取りやすくなります。
・ 受付案内・キャンペーン情報
受付スペースにA4~A3サイズで設置し、キャンペーンやノベルティ配布の案内を表示すること
で、自然にブースへの興味を引けます。
パーテーション掲示活用例
・ ストーリー性のあるパネル配置
横長のパーテーションを活用し、導入→課題→解決策→実績という流れで情報を配置すると、
ストーリー性を持った展示が可能です。
・ 大型パネルでブランド訴求
高さのあるパーテーションには、等身大パネルやB1、B2サイズの大型ボードを掲示すること
で、遠くからの視認性を確保しつつ、ブランディングを強調できます。
注意点とコツ
・ 視線の高さに合わせて掲示することで、読みやすさと訴求力を高められます。
・ 反射や照明の影響を考慮し、光沢紙・マット紙の使い分けも重要です。
・ 掲示器具の安全性や固定強度にも配慮しましょう。特に混雑が予想される会場では、転倒・
落下防止対策も必要です。
掲示方法を工夫することで、単なる情報提示ではなく、展示空間そのものを演出の一部に変えることが可能になります。
来場者を引き込むディスプレイ演出
展示会で成功するためには、単に情報を伝えるだけでなく、来場者の興味を引き、ブースに足を止めてもらうための演出が欠かせません。ここでは、視覚的・空間的な工夫によって展示ブースの印象を高めるディスプレイのポイントを解説します。
効果的なディスプレイ演出の基本
・ 一目で伝わるインパクト重視の構成
パネルやバナー、看板を活用して企業の強みや訴求ポイントを瞬時に伝える演出が重要です。
・ 統一感のあるブース全体設計
パネル、ポスター、卓上物、タペストリーなどすべてのアイテムの色やデザインを統一し、
ブランドの世界観を明確にします。
・ 装飾と空間設計のバランス
パーテーション、照明、小物(植物や展示品)などを使って空間全体を演出することで、記憶に
残るブースが完成します。
・ ブースの「開放感」と「導線」の確保
壁を作り込みすぎず、入退場のしやすい導線設計を心がけることで、来場者が自然と入りやす
くなります。
・ 立体感と奥行きの演出
奥に向かって視線を誘導するレイアウトや、立体的なパネルの配置などにより、印象が深まり
ます。
ディスプレイは視覚だけでなく、空間体験そのものを左右する重要な要素です。「遠くから注目を集め、近づいて納得させる」という設計が求められます。
色・サイズ・ポスター配置のアピール方法
視覚的な訴求力を高めるためには、色の使い方やポスターの配置、サイズの選び方が大きな役割を果たします。それぞれの要素にどのような工夫ができるかを見ていきましょう。
配色とカラー戦略
・ ブランドカラーを中心に構成
展示物全体に統一感を出すためには、自社のコーポレートカラーやサービスのテーマカラー
を基軸に色を構成することが大切です。
・ 視認性の高い補色を活用
キャッチコピーや見出しには背景色とのコントラストを意識し、遠くからでも読みやすくする
必要があります。
・ 色の数を絞る
多色使いは情報が散らばりやすくなるため、メイン・サブ・アクセントの3色程度に抑えるのが
効果的です。
サイズと形状の選び方
・ 遠くからも見える大判サイズの活用
B1、A0などの大きなサイズのパネルやポスターは、離れた位置からの集客に効果を発揮しま
す。
・ 目線の高さを意識した配置
最も見せたい情報は来場者の目線(140〜160cm)に合わせて配置することで、自然な訴求が
可能です。
・ 変形パネルや立体ボードの導入
インパクトを出したい場合には、変形カットや等身大パネルなどを導入することで差別化が
図れます。
ポスターやパネルの配置テクニック
・ ストーリー展開の順に並べる
左から右、上から下へと情報を整理し、視線の流れに沿った配置を心がけると伝わりやすく
なります。
・ 空間にリズムを作る
大・中・小のパネルを組み合わせたり、配置に高低差をつけることで、単調にならない演出が
可能です。
・ 強調すべき情報は中央に
注目させたい要素(例:新商品、キャンペーン、強み)は中央または目線上に配置することで
訴求効果が高まります。
このように、色・サイズ・配置の工夫を重ねることで、視覚的なアピール力は何倍にも高まります。展示空間そのものを「一つの表現媒体」として設計する意識が重要です。
価格と注文時に押さえるポイント
展示会パネルの制作では、価格と注文方法の最適化が全体のコスト効率に大きく影響します。特に限られた予算の中で成果を出すためには、無駄な出費を防ぎ、必要な機能だけを的確に選ぶことが大切です。
価格に影響を与える主な要素
・ サイズ・素材・数量
パネルのサイズが大きくなるほどコストは上がります。素材によっても単価が異なり、スチレン
ボードやファブリックなどは比較的リーズナブルです。一方でアルミや合成紙はやや高価です
が耐久性と表現力に優れるという利点があります。
・ 加工オプションの有無
ラミネート加工、変形カット、穴あけ、フレーム取り付けなどの追加オプションは便利で仕上が
りの質を高める一方、費用が加算されます。必要性を見極めて取捨選択することが重要です。
・ 納期と発送オプション
短納期・当日発送対応には別途料金がかかる場合があり、事前のスケジュール調整で無駄な
急ぎ対応を回避することがコスト削減に繋がります。
・ ロット・一括注文の割引
複数枚を一括で注文すると、ロット割引が適用されることがあります。展示会用だけでなく、
店舗装飾や営業ツールとしても兼用することで、費用対効果を最大化できます。
請求・支払い方法の確認も重要です。
・ 法人対応(請求書払い、後払い、銀行振込など)の有無
・ 代引・カード決済・WEB決済の対応範囲
・ 領収書や帳票類の発行対応
無駄な出費を抑えるには、注文前に仕様・予算・納期を明確にし、見積りを複数社から比較検討することが効果的です。
無駄を省いたプリント対応と販促提案
効率的なプリント対応のコツ
・ テンプレート活用でデザイン費を抑える
多くの印刷会社では、無料テンプレートやレイアウトサンプルが用意されています。自社で一
からデザインを作るのではなく、これらをベースに短期間かつ低コストで仕上げることができ
ます。
・ 修正が少ない入稿データの準備
入稿前に誤字脱字や画像解像度を確認し、校正回数を減らすことで、時間もコストも大幅に
削減可能です。
・ 同時に他アイテムを発注
パネルと一緒にチラシ、バナー、テーブルクロス、サインボードなどを一括で発注すれば、送料
や事務手数料の削減が期待できます
販促に繋がるパネル活用アイデア
・ 等身大パネルで注目度アップ
商品やキャラクターの等身大パネルを設置することで、SNS映えや話題性を創出し、販促に
直結します。
・ QRコード付きの説明パネル
商品詳細ページや特設LPへの動線を設け、紙媒体とWEBを連携させた販促戦略を実現でき
ます。
・ フック付きパネルでノベルティ配布
パネルにフックを付けて、チラシや販促グッズを設置することで、自然な導線で手に取って
もらえます。
コストを抑えながらも効果を最大化するためには、発想の転換と使い方の工夫が不可欠です。パネルは単なる掲示物ではなく、販促ツールとしての戦略的活用が成功を左右します。
まとめ:展示会で差をつけるパネル掲示のコツ
展示会でのパネル掲示は、単なる情報提供を超えて、企業の魅力を最大限に訴求する販促ツールとして活用できます。本記事では、印刷・制作から掲示、ディスプレイ演出に至るまで、パネル活用のコツを幅広く紹介しました。
☞来場者の記憶に残る展示をつくるには「戦略的パネル活用」が鍵です
1. 展示会パネルの基本理解が成果を左右
・ ターゲットと目的を明確にし、情報設計からスタートすることで、伝えたい内容が
ブレずに届きます。
2. 効果的なデザインで訴求力を最大化
・ 視線誘導や配色、配置の工夫によって、パネル単体でも十分なアピールが可能です。
3. 印刷・制作の流れを事前に把握
・ スケジュールや仕様確認を怠らず、無駄なコストやトラブルを防ぐ対応が求められ
ます。
4. 掲示方法の工夫で空間演出が変わる
・ スタンド、パーテーション、卓上など、展示空間に合った掲示方法を選ぶことで、
演出効果が高まります。
5. 販促につながる実践的な活用法を取り入れる
・ QRコード連携や等身大パネル、ノベルティ設置など、パネルを“売れる仕掛け”に
進化させる発想が重要です。
展示会の限られた時間と空間の中で成果を出すためには、「見せ方」だけでなく「伝え方」にも戦略が必要です。来場者の視点に立ったパネル設計と演出によって、他社と差がつく展示を実現しましょう。
お役立ち資料
CASE STUDY
創業以来培ったノウハウとデータをもとにまとめたハンドブックです。
「初めての展示会で何をやったら良いかわからない」「効率的に成果を出すブースづくりについて知りたい」、そんな方におすすめです。
本資料は展示会出展社さま、展示会出展をご検討されている方に向けて作成した資料です。 同業他社さまには資料ダウンロードをご遠慮いただいております。申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。