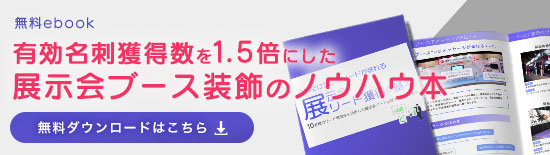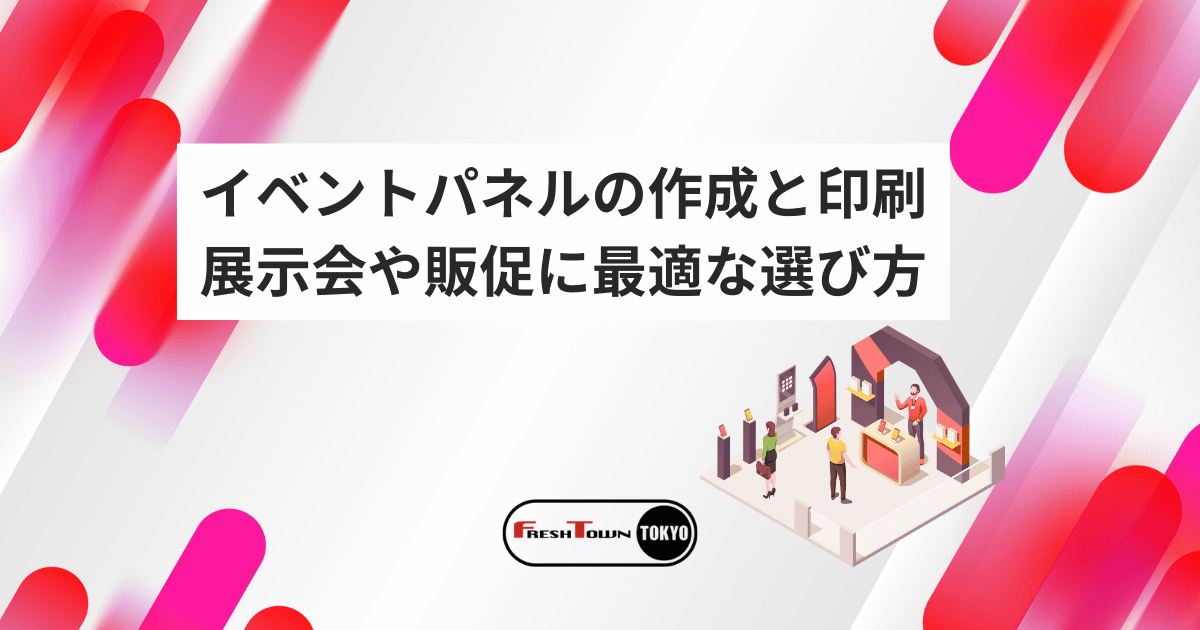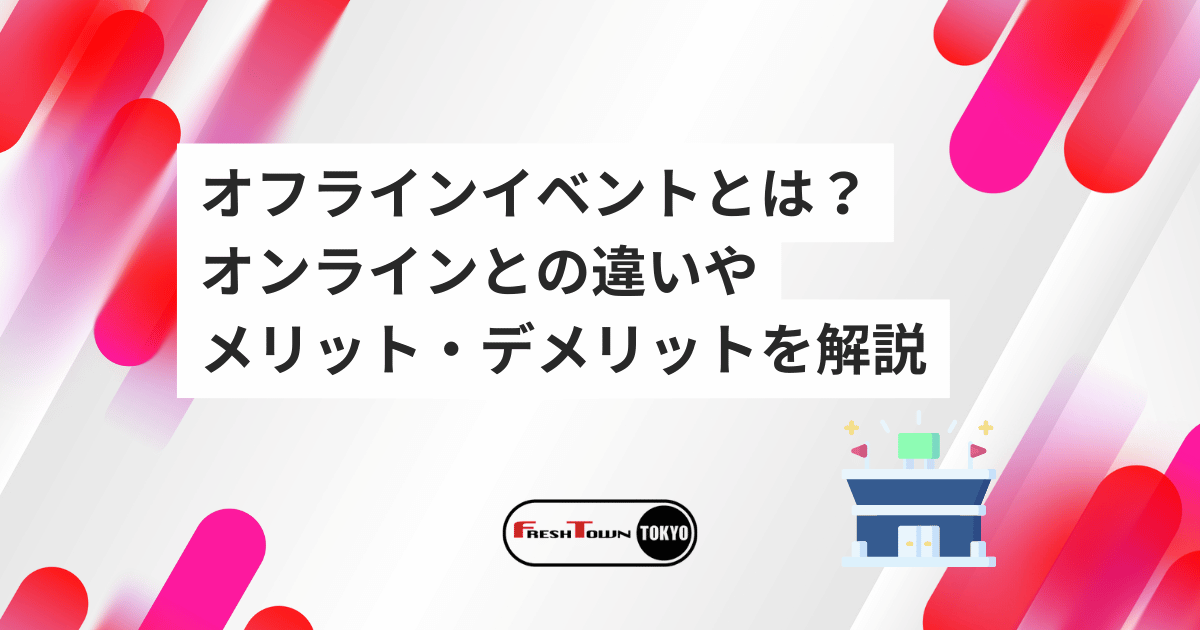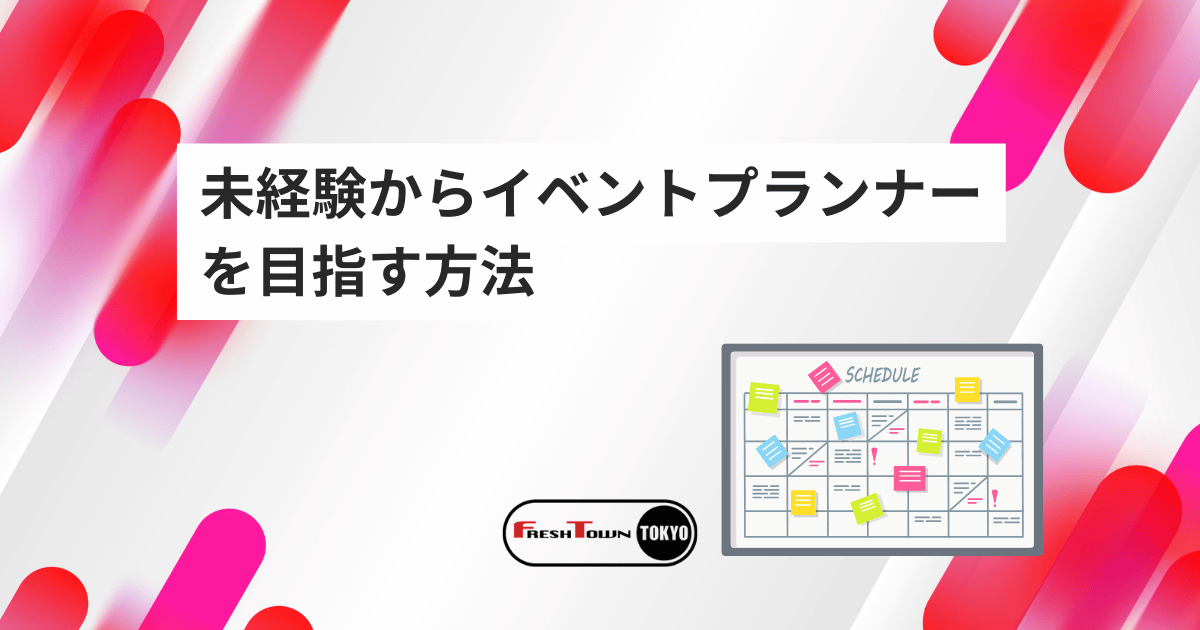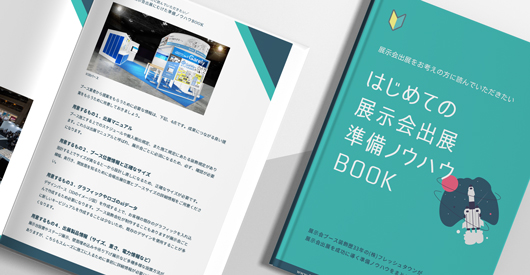【保存版】SaaS展示会出展ガイド2025年版
INDEX

SaaS業界は近年、DXや生成AIといった技術の進展に伴い、企業の業務効率化やデータ活用を目的としたシステム導入が加速しています。こうした流れの中で、SaaS展示会は業界関係者にとって重要なマーケティング・営業機会となっています。展示会は、製品やソリューションを実際に見せながら、来場者と直接対話し、具体的な課題解決策を提案できる場です。
2025年も東京ビッグサイトをはじめ、全国各地で多くのEXPOやイベントが予定されており、出展する企業にとっては商談のチャンスを得る絶好のタイミングとなります。しかし、ただ参加するだけでは成果にはつながりません。効果的な出展には、明確な目的設定、ブースの構成・運営、フォローアップまでを含めた戦略的な準備が不可欠です。
本記事では、展示会への出展を成功に導くために、スケジュールやマーケティング計画の立て方、営業との連携方法、展示内容の構築から当日の対応、そして展示会後の施策に至るまで、実践的なノウハウを網羅的に解説します。
SaaS業界の展示会とは何か?
SaaS業界における展示会は、業種を問わず多くの企業が集まり、自社のソリューションやシステムをアピールするための重要なマーケティング手段です。製品やサービスの紹介だけでなく、商談の場としても機能し、具体的な導入提案や課題解決のきっかけを作ることができます。
こうした展示会は、単なるプレゼンテーションの場ではなく、業界の最新動向や競合の動きを知る情報収集の場でもあります。多くの展示会ではセミナーやパネルディスカッションが併催されており、現場での経営課題やIT活用の現状について深く理解する機会が提供されています。
また、SaaSという製品特性上、来場者がその機能や操作性を体験しやすく、デモンストレーションを通じた導入検討が進みやすいのも特徴です。特にBtoB向けの展示会では、導入権限を持つ経営者や情報システム部門が参加するため、商談の確度が高くなる傾向にあります。
DX推進とSaaS導入の最新潮流
近年、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に向けて取り組みを進めており、それに伴いSaaSの活用が一層広がっています。クラウド型であるSaaSは、スピーディーな導入と柔軟なスケーラビリティが強みであり、人事、経理、EC、データセンター運用など、様々な分野において利用が加速しています。
展示会の現場でも、こうした最新技術や業務効率化ツールの紹介が活発化しており、生成AIや自動化機能を組み込んだSaaS製品が注目を集めています。これらの製品は、単なるシステム導入ではなく、業務プロセス全体を再構築する可能性を持っています。
出展企業にとっては、技術動向を反映した構成や訴求軸を設定することで、より多くの来場者との出会いを生み、検討段階の見込み顧客へ訴求できる機会となります。また、データ連携や他システムとの比較などの切り口も有効です。
展示会が果たすビジネス上の役割とは?
展示会は単なる集客イベントではなく、ビジネス戦略上の重要なタッチポイントです。特にSaaS業界では、オンラインマーケティングとの連携が進む中でも、リアルな会場での接点は、信頼構築や商談成立において欠かせない要素となっています。
主な役割は以下の通りです。
・ 来場者とのリアルな接点構築(直接対話によるニーズ把握)
・ 名刺交換によるリード情報の獲得と分類
・ 製品紹介によるブランド認知と差別化の実現
・ セミナー登壇による専門性の訴求と信頼構築
・ メディアや業界関係者への情報発信機会
さらに、会期中に行われるマッチングサービスや事務局による案内支援なども、出展企業にとっては重要な支援となります。展示会は、単に製品を並べるだけでなく、見込み顧客との最初の接点として、営業プロセスの入口を担う存在であると言えるでしょう。
年間を通じたSaaS展示会スケジュール【2025年版】
SaaS業界の展示会は、年度を通じて全国各地で多数開催されており、会期やエリアによってその特徴も大きく異なります。出展企業にとっては、自社のターゲットに合ったイベントを選ぶことが、集客と成果の鍵となります。
2025年も、国内最大級の総合ITイベントである「Japan IT Week」をはじめ、業種特化型の展示会やデジタルマーケティングに特化した専門イベントなど、多様な形式の展示会が予定されています。東京ビッグサイトや幕張メッセなどの大型会場では、複数の展示会が同時開催されることもあり、来場者との接点が一気に拡大する好機となります。
出展を検討する際には、単に規模の大きさだけでなく、「主催者の狙い」、「来場者の業種・役職」、「出展社数」、「開催地域」などを含めた視点から選定することが重要です。
日本全国の主なEXPO開催概要
2025年に予定されている主なSaaS関連EXPOは以下の通りです。これらの展示会は、それぞれに異なる業界課題や対象者を意識して構成されており、戦略的な出展が求められます。
| イベント | 会期 | 会場/形式 | 入場方法 | 主催 |
|---|---|---|---|---|
| Japan IT Week 春 |
2025年 4月23日 ~25日 |
東京ビッグ サイト 東展示棟 (リアル) |
無料 要登録 |
RX Japan 株式会社 |
| BOXIL EXPO | 2025年 2月18日 ~20日 |
オンライン | 無料 要登録 |
SaaS 比較サイト 「BOXIL」 |
| ビジネス イノベーション Japan 春 |
2025年 2月26日 ~28日 |
幕張メッセ 展示ホール (リアル) |
無料 要登録 |
ビジネス イノベー ションJapan 実行委員会 |
| Business IT & SaaS EXPO (オンライン) |
詳細未定 (公式 サイト 参照) |
過去 オンライン 展示会 として開催 |
無料 要登録 |
Eight (Sansan 株式会社) |
これらの展示会はすでに実績のあるイベントであり、事前の準備とスケジュール管理が成果に直結します。開催1〜2ヶ月前には事務局から案内が届き、出展の可否を決定するタイミングになります。
オンライン展示会との比較と選び方
コロナ禍以降、オンライン展示会の開催も増加しており、リアル展示会との比較検討が必要です。それぞれに特徴とメリットがあるため、出展の目的に応じて選択することが求められます。
オンライン展示会の特徴
・ 地域を問わず参加可能で全国の顧客にアプローチ可能
・ 費用が抑えられ、予算が少ない企業にも対応しやすい
・ データ分析や行動履歴からのリード管理が容易
リアル展示会の特徴
・ 来場者との直接のやりとりが可能で、信頼関係を築きやすい
・ デモやハンズオンで製品の操作性を伝えやすい
・ 名刺交換や対話を通じて深い課題を把握可能
両者を比較した際、SaaS業界では製品デモや業務シナリオの提示が重要なため、リアル展示会のブースでの体験価値が依然として高く評価されています。ただし、プラットフォームの特性や導入フェーズによっては、オンライン施策とのハイブリッド展開が有効です。
出展戦略:営業・マーケ担当者が押さえるべき基本
SaaS展示会で成果を上げるためには、営業部門とマーケティング部門が一体となった戦略設計が欠かせません。ただ「参加する」だけでは、名刺は集まっても商談にはつながりません。重要なのは、目的に沿ってあらかじめ明確なKPIを設定し、それに基づいて展示会全体を構成することです。
さらに、展示会における成功は、事前準備から会場対応、事後フォローまで一貫した営業プロセス設計によって決まります。とくに、見込み顧客の獲得や案件化を狙うなら、営業部門が事前に対象者像を明確にし、マーケティング施策と連動した準備が求められます。
来場者層の分析とターゲティング手法
展示会で最も重要なポイントの一つが、来場者の属性を理解し、自社にとって有効なターゲットを見極めることです。以下のような要素を分析することで、効果的なターゲティングが可能になります。
来場者分析で見るべき指標
・ 職種・部門(情報システム、経営企画、人事、営業など)
・ 業種・業界(製造、流通、小売、サービス、医療など)
・ 課題感・ニーズの傾向(業務効率化、人材管理、顧客データ活用など)
主催者が公開する来場者プロフィールや過去開催のレポートを参考に、ペルソナを設計することが推奨されます。また、ターゲット別の案内状送付や、セグメント別の資料作成など、来場前からの働きかけも成果を左右します。
さらに、ブースの場所選定や展示内容をターゲットに合わせてカスタマイズすることで、より深い接点が期待できます。
出展の目的を明確にするポイント
出展においては、「なぜ出展するのか」という目的の明確化が戦略の土台となります。ここが曖昧だと、社内の準備もぶれやすく、結果として集客や営業成果も中途半端に終わってしまいます。
目的設定では以下のようなポイントを明確にしましょう。
・ 認知向上:ブランド認知や新製品のプロモーションが主目的
・ リード獲得:名刺交換や問い合わせ獲得を重視
・ 商談化:会場内でのヒアリングやマッチングを起点に受注を目指す
・ 市場調査:顧客の反応を見て製品改善や価格設定の参考とする
目的ごとにブース構成、スタッフ体制、配布資料、案内の仕方も変わってきます。特に生成AIや業務改善ツールなど、技術志向の製品を扱う場合は、来場者の課題に即したユースケース提示が非常に有効です。
商談・マッチング機会を最大化する準備
展示会の成果を商談につなげるには、事前準備と当日対応の精度が重要です。特に近年は、展示会主催側によるマッチングサービスや事前アポイント機能が充実しており、それらを有効活用することがポイントです。
商談化を促進するための施策
・ 来場予定者への事前アプローチ(メール、電話、DM等)
・ ブース内での個別商談スペースの設置
・ 営業担当のローテーションと役割分担
・ オンライン連携による後追い支援体制の構築
また、Web予約フォームやQRコード登録など、デジタルを活用した仕組みも積極的に取り入れるべきです。来場者の行動データをその場で記録し、営業支援ツールにリアルタイム連携させることで、展示会終了後のスムーズなフォローアップが可能になります。
展示会での商談数を最大化する方法について詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会で商談数を最大化する方法とは?|商談獲得を成功に導く5つの秘訣も是非ご一読ください。
フレッシュタウンの展示会支援サービス
BtoB向け展示会のプロフェッショナルとして、フレッシュタウンは年間1,300件以上の展示会をワンストップでサポートしています。
「名刺獲得数最大化」と「ブース体験最大化」をテーマに、企画・デザイン、施工から会期後のフォローまで自社完結で提供し、大手企業からスタートアップまで幅広くご好評をいただいています。
フレッシュタウンが選ばれる3つの理由
1. 専属担当によるリード獲得戦略
BtoBマーケティングのノウハウを持つ専属営業が、貴社の課題に応じた最適な集客プランを提案します。
2. 自社デザイナーによる柔軟なデザイン力
社内のデザイナー体制で、企業イメージを高めながら来場者を惹きつけるブースを設計します。
3. ワンストップ施工&フォロー体制
企画から施工、会期後の振り返りまで自社内で完結。次回コストダウンも視野に入れた継続サポートが可能です。
成果を出すブース設計と運営の工夫
展示会ブースは単なる製品陳列の場ではなく、来場者との最初の接点を生み出す“体験空間”です。そのため、企業の顔としての役割を果たすブース設計は、出展成功の成否を分ける重要な要素となります。
魅力的なブースには、以下の3つの要素がバランスよく構成されています。
1. 視認性の高さ(遠くからでも目を引くデザイン)
2. 導線の工夫(来場者が自然と立ち寄れるレイアウト)
3. 情報伝達の明確さ(一目で提供価値が伝わる訴求)
さらに、現場での対応力や案内の質も、印象や信頼感に直結します。営業担当者だけでなく、マーケティング部門や開発部門など、専門知識を持つスタッフの配置も効果的です。
来場者を惹きつけるブースのデザインとは
来場者が多数訪れる展示会において、第一印象を決めるのはブースの外観です。どれほど優れた製品でも、目に留まらなければ話は始まりません。効果的なブースデザインには、以下の視点が欠かせません。
注目を集めるブース設計のポイント
・ 製品の特徴や導入効果が一目でわかるキャッチコピー
・ 照明や配色で視認性を高めた外装
・ デモスペースや大型モニターを活用した視覚訴求
・ 企業カラーやロゴを活かした統一感のある構成
また、展示内容を絞り込み、情報過多にならないことも重要です。ターゲットが必要とする情報だけを強調することで、ブース内での滞在時間や名刺交換の機会も増加します。
ブース設計には、社内デザイナーだけでなく、展示会に特化した外部パートナー企業の力を借りるのも有効な手段です。
展示会のブース設営の流れや考え方について詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会のブース設営マニュアル|ブース装飾・施工の流れとは?も是非ご一読ください。
生成AI・AI活用による案内や接客の効率化
展示会では、短時間に多くの来場者に対応する必要があり、案内業務や質問対応の効率化が課題となります。ここで活用が進んでいるのが、生成AIやチャットボットを組み込んだツールの導入です。
AIによる案内・接客のメリット
・ 対応の標準化によってサービス品質のばらつきを防止
・ 人手不足の補完として多数の来場者に同時対応可能
・ 来場者データのリアルタイム収集により営業活動に直結
たとえば、AIが来場者の属性や興味関心を判断し、最適な資料を提示したり、適切な担当者へ案内する仕組みが実現されています。こうしたツールは、会期中の混雑対応や、会場全体の効率化にも貢献します。
また、近年では多言語対応や音声認識機能も進化しており、インバウンド来場者への対応にも有効です。
展示会場でのリアルタイム営業支援
展示会当日は、いかに現場の営業活動を即座に成果につなげるかが勝負になります。従来は、名刺を集めて後日アプローチという流れが主流でしたが、現在ではその場で見込み度の高い顧客を即時に把握・記録する仕組みが整いつつあります。
リアルタイム支援で可能になること
・ QRコードスキャンによる名刺情報のデータ化
・ 来場者の興味関心情報の即時入力と分類
・ CRMやSFAとの連携による営業スピードアップ
・ 来場履歴を活かしたフォロータイミングの最適化
このように、ITツールを活用した営業支援により、展示会は「後追い型」から「即時対応型」へと変化しています。特にBtoB領域では、このスピード感が案件化率を大きく左右するため、準備段階から体制を整えておく必要があります。
展示会で営業成果を最大化する方法について詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会で営業成果を最大化するためのコツとは?|結果に直結するポイントも是非ご一読ください。
展示会後のフォローアップと営業連携
展示会での成果は、会場での名刺交換や商談だけでは完結しません。真の成果は、展示会後のフォローアップを通じて、見込み顧客との関係を育て、最終的に受注につなげることで初めて得られます。
展示会後の行動は「営業活動の第2ステージ」と位置付けられ、いかに早く・的確に・継続的にアプローチを行えるかが成果を左右します。営業とマーケティング部門が連携し、会場で得られた情報を最大限に活かす体制が求められます。
名刺交換だけで終わらせない顧客対応の極意
展示会で得た名刺は、単なる連絡先リストではなく、今後の営業機会への入口です。しかし、単に名刺を管理するだけでは十分ではありません。
顧客対応のポイント
・ 名刺情報をすぐにデータ化し、CRMに登録
・ 交換時の会話内容や関心テーマを記録し、パーソナライズ対応へ反映
・ 会期後1〜3営業日以内にメールや電話でフォローアップ
・ 役職や部署に応じてアプローチ内容をカスタマイズ
対応が遅れると、他社に商談機会を奪われる可能性もあるため、スピード感と個別対応が鍵になります。また、資料請求フォームやウェビナー案内などのコンテンツ連携も効果的です。
オンライン活用による商談継続とナーチャリング
展示会の後は、オンライン施策を活用してナーチャリング(育成)を行うフェーズに入ります。展示会で興味を示したものの、すぐには導入に至らない層に対して、継続的に情報を提供し購買意欲の向上を図ることが目的です。
ナーチャリング施策の例
・ 展示会後に特化したサンクスメールやフォローメール
・ 製品比較資料や導入事例など課題解決型コンテンツの配信
・ ウェビナー開催や個別オンライン商談の案内
・ 閲覧データの分析に基づいたスコアリングと再アプローチ
これらの施策は、マーケティングオートメーションツールやWebプラットフォームと連動させることで、効率的かつ継続的な接点維持が可能になります。
展示会後のフォローについて詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会後のフォローを成功させる方法とは?|フォローから商談獲得も是非ご一読ください。
効果測定と次年度への改善アクション
展示会が終了した後は、レポート作成と効果分析を行い、次回への改善点を洗い出すことが欠かせません。出展目的に応じた成果指標(KPI)をもとに、どこまで達成できたかを振り返ります。
測定すべき主なKPI
・ 名刺獲得枚数と対象者の質
・ 商談件数および受注見込み件数
・ 来場者の反応や質問内容
・ アンケート結果・展示資料のダウンロード数
また、出展にかかった費用と得られた成果を照らし合わせ、ROI(投資対効果)を可視化することで、社内報告や次回の出展判断にも役立ちます。
さらに、他社の展示内容や出展位置の有利・不利、来場者の動線といった要素も振り返りのポイントです。こうした情報は社内共有だけでなく、来年以降の展示会戦略構築にも貴重な材料となります。
展示会の効果測定ついて詳しく解説している記事もご紹介します。
展示会の効果測定の方法とは?効果を可視化してROIを改善も是非ご一読ください。
まとめ:展示会で成果を出すための最重要ポイント
■展示会は準備からフォローまでが勝負。全体設計と現場対応の精度が成果を左右します。
展示会は一過性のイベントではなく、戦略的なマーケティング活動の一環として取り組むべきものです。成功の鍵は、計画、実行、改善のサイクルを丁寧に回し続けることにあります。以下に本記事で紹介した重要ポイントを改めてまとめます。
☞展示会成功のための重要ポイント
1. 出展目的の明確化
・ 新規顧客の獲得、製品の認知拡大、商談件数の増加など、明確なKPIを設定
2. ターゲット来場者の分析と選定
・ 過去の来場データや主催者情報を活用し、対象となる顧客像を明確化
3. 適切な展示会の選定とスケジュール管理
・ 地域、会場、来場者層、業種とのマッチングを重視し、出展機会を厳選
4. ブース設計とデザインの工夫
・ 来場者の動線や視認性を意識したレイアウトと、訴求力のあるキャッチコピーを用意
5. AI・生成AIの活用による業務効率化
・ 案内や商談補助、リードデータの取得などでテクノロジーを有効活用
6. 名刺交換後の即時フォローとナーチャリング体制の構築
・ 展示会後の営業連携を強化し、ホットリードへの対応スピードを重視
7. レポート・振り返りによる次回改善
・ 効果測定を行い、社内での成果共有と次回出展計画への反映を徹底
展示会は、リアルとデジタルが交差する貴重な顧客接点です。SaaS業界のように競争が激しい領域では、的確な出展戦略が成果を左右します。この記事をもとに、ぜひ自社に最適な展示会施策を設計し、来場者との価値ある出会いを創出してください。
Q&A
SaaSの展示会に出展する主なメリットは何ですか?
新規顧客の獲得、製品認知の拡大、商談機会の創出、競合との比較優位の訴求が可能です。リアルな対話を通じて高精度なニーズ把握ができる点も大きなメリットです。
出展前に準備しておくべきことは何ですか?
目的設定、ターゲット分析、ブース設計、配布資料の作成、スタッフ配置、営業フォロー体制の整備、そして主催者との連携確認などが重要です。
オンライン展示会とリアル展示会のどちらを選ぶべきですか?
ターゲット層や目的により異なります。デモ体験や商談重視ならリアル、コストやリーチの広さ重視ならオンラインが適しています。ハイブリッド展開も有効です。
展示会での名刺交換後はどのような対応が効果的ですか?
速やかなメールや電話によるフォローアップ、関心に応じた情報提供、スコアリングによる優先順位づけ、営業への即時連携が効果的です。
展示会の効果測定はどのように行えば良いですか?
獲得名刺数、商談数、成約数、来場者属性の分析、費用対効果(ROI)、アンケート結果などを数値化し、レポートとしてまとめることで次回の改善につながります。
お役立ち資料
CASE STUDY
創業以来培ったノウハウとデータをもとにまとめたハンドブックです。
「初めての展示会で何をやったら良いかわからない」「効率的に成果を出すブースづくりについて知りたい」、そんな方におすすめです。
本資料は展示会出展社さま、展示会出展をご検討されている方に向けて作成した資料です。 同業他社さまには資料ダウンロードをご遠慮いただいております。申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。